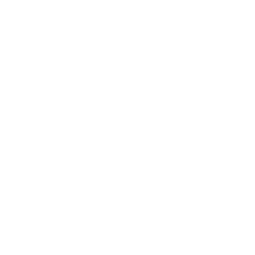
- Ebenholz
- 黑键
- 에벤홀츠
エーベンホルツ
術師タイプ — 秘術師
敵に術ダメージを与える
攻撃の対象がいない場合はエネルギーをチャージして(最大3回)次の攻撃時に一斉発射する
攻撃の対象がいない場合はエネルギーをチャージして(最大3回)次の攻撃時に一斉発射する
- LN05
- 遠距離
- 火力
ボーナスを含む
HP
1678
攻撃力
1550
防御力
135
術耐性
20
配置コスト
25
攻撃間隔
3 秒
ブロック数
1
再配置時間
70 秒
素質
- デュナーミクチャージした攻撃エネルギーのダメージが135%まで上昇、【エリート】または【ボス】のみに攻撃可能な攻撃エネルギーを追加で1つ分チャージ可能
- アポジャトゥーラ攻撃対象の周囲に他の敵がいない場合、攻撃時に追加で攻撃力の15%の術ダメージを与える
スキル
設定で詳細一覧を有効にして、詳細データが表示されます。
 アッチェレランド自動回復手動発動初期SP5必要SP15継続時間5 秒攻撃範囲変化、攻撃間隔を超大幅に短縮し、通常攻撃時、敵に攻撃力の50%の術ダメージを与えるbase_attack_time0.17attack@atk_scale0.5attack@cnt1
アッチェレランド自動回復手動発動初期SP5必要SP15継続時間5 秒攻撃範囲変化、攻撃間隔を超大幅に短縮し、通常攻撃時、敵に攻撃力の50%の術ダメージを与えるbase_attack_time0.17attack@atk_scale0.5attack@cnt1 旧日の残響自動回復自動発動必要SP13全ての攻撃エネルギーを消費し、攻撃範囲内の配置可能マスに消費エネルギー数+1体の「過去の残像」を召喚(30秒継続)、残像は敵が接近時に発動し、周囲の敵に攻撃力の245%の術ダメージを与え、相当の力で敵を自身の中心に引き寄せるatk_scale2.45force1
旧日の残響自動回復自動発動必要SP13全ての攻撃エネルギーを消費し、攻撃範囲内の配置可能マスに消費エネルギー数+1体の「過去の残像」を召喚(30秒継続)、残像は敵が接近時に発動し、周囲の敵に攻撃力の245%の術ダメージを与え、相当の力で敵を自身の中心に引き寄せるatk_scale2.45force1
過去の残像
HP1000攻撃力100防御力0術耐性0配置コスト0攻撃間隔1 秒ブロック数0再配置時間0 秒 フラッシュバック自動発動敵が接近時に発動し、発動時周囲の敵全員に術ダメージを与え、相当の力で敵を自身の中心に引き寄せるatk_scale2.45force1
フラッシュバック自動発動敵が接近時に発動し、発動時周囲の敵全員に術ダメージを与え、相当の力で敵を自身の中心に引き寄せるatk_scale2.45force1 無響の声自動回復手動発動初期SP10必要SP20継続時間30 秒攻撃速度+80、攻撃力+65%、エリートまたはボスのみを攻撃対象とし、第一素質のダメージ上昇効果を元々の140%まで上昇
無響の声自動回復手動発動初期SP10必要SP20継続時間30 秒攻撃速度+80、攻撃力+65%、エリートまたはボスのみを攻撃対象とし、第一素質のダメージ上昇効果を元々の140%まで上昇
手動でスキルを停止可能attack_speed80atk0.65talent_scale_multiplier1.4
モジュール
 ORIGINALエーベンホルツの記章
ORIGINALエーベンホルツの記章 MSC-X源石ダイス収納箱
MSC-X源石ダイス収納箱STAGE ステータス 強化説明 1 - 攻撃力 +58
- 攻撃速度 +3
秘術師の特性 敵に術ダメージを与える
攻撃の対象がいない場合はエネルギーをチャージして(最大4回)次の攻撃時に一斉発射する2 - 攻撃力 +75
- 攻撃速度 +4
デュナーミク チャージした攻撃エネルギーのダメージが140%まで上昇、エリートまたはボスのみに攻撃可能な攻撃エネルギーを追加で1つ分チャージ可能3 - 攻撃力 +90
- 攻撃速度 +5
デュナーミク チャージした攻撃エネルギーのダメージが143%まで上昇、エリートまたはボスのみに攻撃可能な攻撃エネルギーを追加で1つ分チャージ可能 MSC-Y「楽理解釈者」
MSC-Y「楽理解釈者」STAGE ステータス 強化説明 1 - HP +80
- 攻撃力 +88
秘術師の特性 敵に術ダメージを与える
攻撃の対象がいない場合はエネルギーをチャージして(最大3回)次の攻撃時に一斉発射する攻撃エネルギーがある時、攻撃速度+302 - HP +120
- 攻撃力 +112
アポジャトゥーラ 攻撃対象の周囲に他の敵がいない場合、攻撃時に追加で攻撃力の18%の術ダメージを与える。他の敵がある場合、攻撃対象の周囲にいる敵全員に自身の攻撃力の25%の術ダメージを与える3 - HP +175
- 攻撃力 +135
アポジャトゥーラ 攻撃対象の周囲に他の敵がいない場合、攻撃時に追加で攻撃力の20%の術ダメージを与える。他の敵がある場合、攻撃対象の周囲にいる敵全員に自身の攻撃力の36%の術ダメージを与える MSC-Δ朽ちた伝承
MSC-Δ朽ちた伝承STAGE ステータス 強化説明 1 - 攻撃力 +76
- 術耐性 +4
秘術師の特性 敵に術ダメージを与える
攻撃の対象がいない場合はエネルギーをチャージして(最大3回)次の攻撃時に一斉発射する術ダメージを与えたとき、追加で与ダメージの8%の壊死損傷を与える2 - 攻撃力 +102
- 術耐性 +5
アポジャトゥーラ 攻撃対象の周囲に他の敵がいない場合、攻撃時に追加で攻撃力の24%の術ダメージを与える。攻撃対象が壊死損傷の爆発効果中の場合、攻撃時に追加で攻撃力の20%の元素ダメージを与える3 - 攻撃力 +124
- 術耐性 +5
アポジャトゥーラ 攻撃対象の周囲に他の敵がいない場合、攻撃時に追加で攻撃力の30%の術ダメージを与える。攻撃対象が壊死損傷の爆発効果中の場合、攻撃時に追加で攻撃力の30%の元素ダメージを与える
基地スキル
 音感製造所配置時、宿舎中のオペレーター1人につき、知覚情報+1。1の知覚情報が1の静かなる共鳴に転化される
音感製造所配置時、宿舎中のオペレーター1人につき、知覚情報+1。1の知覚情報が1の静かなる共鳴に転化される 彷徨う旋律貿易所配置時、静かなる共鳴4につき、受注効率+1%
彷徨う旋律貿易所配置時、静かなる共鳴4につき、受注効率+1% 茫然たる和声
茫然たる和声 貿易所配置時、静かなる共鳴2につき、受注効率+1%
貿易所配置時、静かなる共鳴2につき、受注効率+1%



