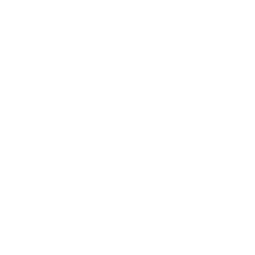
- Totter
- 铅踝
- 토터
トター
狙撃タイプ — 破城射手
重量が最も重い敵を優先して攻撃
- SG11
- 遠距離
- 火力
ボーナスを含む
【コードネーム】トター
【性別】男
【戦闘経験】二十年
【出身地】サルゴン
【誕生日】6月21日
【種族】リーベリ
【身長】185cm
【鉱石病感染状況】
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。
【性別】男
【戦闘経験】二十年
【出身地】サルゴン
【誕生日】6月21日
【種族】リーベリ
【身長】185cm
【鉱石病感染状況】
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。
【物理強度】普通
【戦場機動】欠落
【生理的耐性】標準
【戦術立案】標準
【戦闘技術】標準
【アーツ適性】標準
【戦場機動】欠落
【生理的耐性】標準
【戦術立案】標準
【戦闘技術】標準
【アーツ適性】標準
トターはヴィクトリア辺境の森に住まう半引退状態の傭兵であり、本名もサルゴン語で同音である。世話になった相手へ義理を返すために森を離れ、大きな危険を冒してロンディニウムの戦場にやってきた。事件後、狙撃手として時々ロドスの外勤任務に参加している。
造影検査の結果、臓器の輪郭は不明瞭で異常陰影も認められる。循環器系源石顆粒検査の結果に異常があり、鉱石病の兆候が認められる。以上の結果から、鉱石病感染者と判定。
【源石融合率】7.8%
左足首に源石結晶の分布が見られる。
【血液中源石密度】0.24u/L
病状は安定しており、悪化の傾向は見られないが、病理的な原因による足首の変化によって、歩行能力が多少損なわれている。
【源石融合率】7.8%
左足首に源石結晶の分布が見られる。
【血液中源石密度】0.24u/L
病状は安定しており、悪化の傾向は見られないが、病理的な原因による足首の変化によって、歩行能力が多少損なわれている。
トターが艦内に滞在する時間はかなり少ない。任務の報告と定期検査のために帰還する時以外の時間は、ヴィクトリアの森にあるウッドハウスで過ごすか、任務の遂行にあてている。
トターと関わりを持つオペレーターも多くはない。だが彼と共に任務にあたったことがある者は例外なく、トターが見せる洞察力と実務能力を評価しているし、彼が参加すると任務の達成率が明らかに上昇する。手ごわい任務であっても、トターがコーディネートし、優先順位をつけた上で、中間目標を設定してそれを段階的にクリアをしていくと、結果は大抵望ましいものになるのだ。彼のそういった仕事の進め方に対して、システマチックで融通が効かないと文句をこぼす者もいたが、気力に限界があり、足が不自由なトターにとっては、このやり方こそが限られた選択肢の中の最善であるのだ。
ロンディニウム事件を実際に経験したことで、トターは血生臭い稼業から足を洗って完全に引退することを決意した。ヴィクトリア北部、雪境に近い無人の森に戻り、狩人という元々の仕事で生計を立てることにしたそうだ。今のトターは見るからに温厚で穏やかであり、生活の中で起こるどんな出来事に対しても気持ちを乱されることなく過ごしている。戦塵も、消毒液や錆びた鉄の匂いも、絶えない悲鳴も彼の生活からは消え去った。代わりに姿を見せるのは、薪、熱いお茶と松の香り、そしてギュッと雪を踏みしめた音である。
だが時折見せる洗練された冷徹な仕事ぶりは、長い時間をかけて彼に染み込んだものを垣間見せる。それらは再度呼び起こされる機会を静かに待っているのだ。本人の意志に関わらず、簡単に変わることのない事実である。
トターと関わりを持つオペレーターも多くはない。だが彼と共に任務にあたったことがある者は例外なく、トターが見せる洞察力と実務能力を評価しているし、彼が参加すると任務の達成率が明らかに上昇する。手ごわい任務であっても、トターがコーディネートし、優先順位をつけた上で、中間目標を設定してそれを段階的にクリアをしていくと、結果は大抵望ましいものになるのだ。彼のそういった仕事の進め方に対して、システマチックで融通が効かないと文句をこぼす者もいたが、気力に限界があり、足が不自由なトターにとっては、このやり方こそが限られた選択肢の中の最善であるのだ。
ロンディニウム事件を実際に経験したことで、トターは血生臭い稼業から足を洗って完全に引退することを決意した。ヴィクトリア北部、雪境に近い無人の森に戻り、狩人という元々の仕事で生計を立てることにしたそうだ。今のトターは見るからに温厚で穏やかであり、生活の中で起こるどんな出来事に対しても気持ちを乱されることなく過ごしている。戦塵も、消毒液や錆びた鉄の匂いも、絶えない悲鳴も彼の生活からは消え去った。代わりに姿を見せるのは、薪、熱いお茶と松の香り、そしてギュッと雪を踏みしめた音である。
だが時折見せる洗練された冷徹な仕事ぶりは、長い時間をかけて彼に染み込んだものを垣間見せる。それらは再度呼び起こされる機会を静かに待っているのだ。本人の意志に関わらず、簡単に変わることのない事実である。
本艦の教官は、トターのことを天性の狙撃手と評価した。理想的な気候条件の中であれば、遠視であるトターは百メートル先のターゲットでさえ簡単に捕捉できる。さらに、裸眼だけでターゲットの細かな動きを捉え、ターゲットを視認した瞬間に精度の高い判断で射殺することも可能である。
幼い頃身に着けた狩猟の技術は、彼が狙撃手の道に進むにあたって大いに役立った。トターはサルゴンのジャングルで暮らす小さな部族の出身である。辺地に位置するそこは現代文明から遠く離れているが、部族の狩人たちが代々伝えてきた狩猟技術は研ぎ澄まされていた。トターの親の世代は皆、部族内の優秀で経験豊かな狩人たちであり、彼らは地形の認識、天気の判断や獲物の識別などの知識を、幼いトターにすべて伝授した。トターも期待を裏切ることなく、教えられたことを素早く吸収し、同輩の中でも突出して優れた狩人になった。さらに、彼はもう一つの素質を有していた――すなわち、我慢強さである。湿った蒸し暑いジャングルの中で静かに潜伏し続けることは不可能であるかのように思えるが、トターはその非凡な我慢強さで、獲物が射程に入ってくるのを一日中微動だにせず待ち続けることができる。それは、のちに傭兵としてもトターの人生で役立つ素質だった。
成年後、トターは傭兵狙撃手としてサルゴンやクルビア、ヴィクトリアを転々とし、各地を歩き渡ってきた。その中には、条件が悪劣で、情勢も複雑な作戦環境も少なくなかった。しかし標的を仕留めるためであれば、トターは酷寒の冬に一人で雪山の深くに赴き数日待ち続けることも、燦々とした日差しの中で微動だにせず熱い砂場に伏し続けることも厭わない。他の者からすれば何の面白味もなく、ただ孤独に待機し続けるその辛い過程を、トターは一度も報告書に記したことがなく、いつも最後に一言「任務完了」と簡潔に書いて終わらせるだけだった。
武器に関しても、トターは独自のこだわりがある。彼は臂力が強く、用いる矢もすべて部族の狩猟専用の矢から改造したものである。それは大型の標的を仕留めることに特化している。このような大威力の矢は戦場において、何度も前線オペレーターの重圧を大幅に軽減してくれた。
幼い頃身に着けた狩猟の技術は、彼が狙撃手の道に進むにあたって大いに役立った。トターはサルゴンのジャングルで暮らす小さな部族の出身である。辺地に位置するそこは現代文明から遠く離れているが、部族の狩人たちが代々伝えてきた狩猟技術は研ぎ澄まされていた。トターの親の世代は皆、部族内の優秀で経験豊かな狩人たちであり、彼らは地形の認識、天気の判断や獲物の識別などの知識を、幼いトターにすべて伝授した。トターも期待を裏切ることなく、教えられたことを素早く吸収し、同輩の中でも突出して優れた狩人になった。さらに、彼はもう一つの素質を有していた――すなわち、我慢強さである。湿った蒸し暑いジャングルの中で静かに潜伏し続けることは不可能であるかのように思えるが、トターはその非凡な我慢強さで、獲物が射程に入ってくるのを一日中微動だにせず待ち続けることができる。それは、のちに傭兵としてもトターの人生で役立つ素質だった。
成年後、トターは傭兵狙撃手としてサルゴンやクルビア、ヴィクトリアを転々とし、各地を歩き渡ってきた。その中には、条件が悪劣で、情勢も複雑な作戦環境も少なくなかった。しかし標的を仕留めるためであれば、トターは酷寒の冬に一人で雪山の深くに赴き数日待ち続けることも、燦々とした日差しの中で微動だにせず熱い砂場に伏し続けることも厭わない。他の者からすれば何の面白味もなく、ただ孤独に待機し続けるその辛い過程を、トターは一度も報告書に記したことがなく、いつも最後に一言「任務完了」と簡潔に書いて終わらせるだけだった。
武器に関しても、トターは独自のこだわりがある。彼は臂力が強く、用いる矢もすべて部族の狩猟専用の矢から改造したものである。それは大型の標的を仕留めることに特化している。このような大威力の矢は戦場において、何度も前線オペレーターの重圧を大幅に軽減してくれた。
「トターさん、眼鏡が出来上がりました。かけてみますか?最初はめまいがするかもしれませんが、よくあることです。立ち上がって少し歩いてみれば慣れると思います。」
「ああ、よく見える。」
「あの、ずっと見つめていらっしゃいますが、私がどうかしました?」
「目やにが付いているのに気付いてな、光を反射して輝いている。」
「……目やにではありません。これはハイライトです。」
「すまない、わざとじゃないんだ。」
「はあ、もういいです。どうしてこんな話に……いかがですか、眼鏡をかけてからやってみたいこととかありますか?」
「本を読むことかな? 久しぶりなんだ。」
「いい考えですね。読書好きとは意外でした。」
「いや、好きではない。紙に小さい文字がびっしりで、見続けると目が疲れる。」
「私をからかってるんですか?」
「そんなことはないさ。昨日、艦内で何人かのオペレーターが会議室で最近読んだ本の話をしているところに居合わせたんだ。すごく盛り上がっていて楽しそうだった。」
「そのうち一人が俺に気付いて、話に誘ってくれたんだ。だが俺は本を読まない。ウッドハウスにはボロのラジオしかなくて、聞こえてくる声はどちらかというとノイズのようなものだ。基本的には天気予報を聞く程度しか使ってない。」
「だからちっとも話に混じれずにあいつらの討論を聞くことしかできなかったんだ。わからないことばかりだったが、興味深かった。」
「内容に興味を持ったから、自分でも読んでみたくなったってことですか?」
「違う。」
「共有会が終わった時、俺もこっそり抜けようとしたんだが、一人の娘が俺を呼び止めたんだ。本を渡して、この本に関する感想を聞きたい、と。そして……次も参加してほしいと。他の奴らにもそう言われた。」
「……トターさん、前回ご自身のウッドハウスを離れるのはいつ頃でしたか?」
「大体半年前かな。」
「その間、ずっとお一人で?」
「ああ。」
「……」
「お帰りになったら、暗い照明のもとで本を読まないように気を付けてください。目に良くないですから。」
「ああ、覚えておく。ありがとうな、先生。」
「ああ、よく見える。」
「あの、ずっと見つめていらっしゃいますが、私がどうかしました?」
「目やにが付いているのに気付いてな、光を反射して輝いている。」
「……目やにではありません。これはハイライトです。」
「すまない、わざとじゃないんだ。」
「はあ、もういいです。どうしてこんな話に……いかがですか、眼鏡をかけてからやってみたいこととかありますか?」
「本を読むことかな? 久しぶりなんだ。」
「いい考えですね。読書好きとは意外でした。」
「いや、好きではない。紙に小さい文字がびっしりで、見続けると目が疲れる。」
「私をからかってるんですか?」
「そんなことはないさ。昨日、艦内で何人かのオペレーターが会議室で最近読んだ本の話をしているところに居合わせたんだ。すごく盛り上がっていて楽しそうだった。」
「そのうち一人が俺に気付いて、話に誘ってくれたんだ。だが俺は本を読まない。ウッドハウスにはボロのラジオしかなくて、聞こえてくる声はどちらかというとノイズのようなものだ。基本的には天気予報を聞く程度しか使ってない。」
「だからちっとも話に混じれずにあいつらの討論を聞くことしかできなかったんだ。わからないことばかりだったが、興味深かった。」
「内容に興味を持ったから、自分でも読んでみたくなったってことですか?」
「違う。」
「共有会が終わった時、俺もこっそり抜けようとしたんだが、一人の娘が俺を呼び止めたんだ。本を渡して、この本に関する感想を聞きたい、と。そして……次も参加してほしいと。他の奴らにもそう言われた。」
「……トターさん、前回ご自身のウッドハウスを離れるのはいつ頃でしたか?」
「大体半年前かな。」
「その間、ずっとお一人で?」
「ああ。」
「……」
「お帰りになったら、暗い照明のもとで本を読まないように気を付けてください。目に良くないですから。」
「ああ、覚えておく。ありがとうな、先生。」
トターは自身の雪好きを他人の前で隠したりしない。彼のウッドハウスには、スノードームをコレクションするための専門の部屋がある。常に身に着けているクロスボウにも、雪の結晶の飾りが付けてある。それどころか、彼が提出する経費の精算申請には、いつもスノードーム購入費の項目がこっそり仕込まれるほどである。
交流記録を参照する限り、トターは自らの雪好きは子供時代に見た雪の結晶の標本が原因だと考えているようだ。ヴィクトリアの商隊がジャングルの部族を通りかかった時に残したもので、その精密で美しい構造は、雪を見たことがないトターが商人たちが口にする雪景色に憧れを抱くのに十分なものだった。それがきっかけで外の世界に思いを馳せるようになり、部族に残るという考えを覆して、成年後に故郷を離れることにしたのだという。
しかし始まりは一片の雪花だったとしても、いつしか分厚い雪に覆い尽くされてしまうものである。
故郷を離れたトターは気の合う友人に出会い、共に自分たちだけの傭兵団を立ち上げた。しっかりと訓練を積んだ戦闘員を多く擁する傭兵団は、段々と規模を大きくしていき、名も通るようになった。だが、何もかもが上手く進んでいる時に発生した事故によって、傭兵団はその構成員の半数を失ってしまった。トターもその一件で鉱石病に感染し、歩行能力をほぼ失ってしまったのだという。傭兵団と共に進めなくなった彼は森の奥に取り残された。雪境に近いその森は頻繁に吹雪に見舞われていた。晴れていたはずなのに、次の瞬間は予兆もなく、暴風が氷雪を携えて襲ってくるのだ。
トターは、傭兵団を抜けてから随分と長い間、かなり落ち込んでいたと吐露した。それが止まったのは、ある日痛み止めのせいで眠気に襲われていた時の出来事のおかげだった。窓を破らんと暴れる吹雪がウッドハウスの外で吹き荒れていたのが、いつしか収まり、辺りは静寂に包まれた。久々の日差しが彼の閉じた瞼に降り注ぎ、まとわりつく悪夢から彼を目覚めさせた。そして彼は窓の外を眺めた。無限に広がる真っ白な森に、数本の葉が落ちた真っ直ぐな杉の木が雲一つない空に突き刺さっていた。そんな景色の中から、トターは久々に落ち着いた気分を取り返すことができたのだという。置いていかれたことに苦しむことがようやくなくなり、自らに降りかかった不幸に対しても達観することができるようになったそうだ。
しかし会話の最中、トターはずっと下に目を向け、何度も唇を舐めていた。明らかに何か隠している反応だった。数度問い詰めたが、結局は明かしてくれず、会話にも拒絶の態度を見せ始めた。
そんなトターの反応は私に不安を覚えさせるものだった。積もった雪の下に覆い隠されたのは、彼の絶望と苦しみだけではないかもしれない。私はどうしても恐ろしい想像が思い浮かんでしまう。あの無垢な雪原を、あの極寒の冬を、彼は本当に抜け出せているのだろうか?
交流記録を参照する限り、トターは自らの雪好きは子供時代に見た雪の結晶の標本が原因だと考えているようだ。ヴィクトリアの商隊がジャングルの部族を通りかかった時に残したもので、その精密で美しい構造は、雪を見たことがないトターが商人たちが口にする雪景色に憧れを抱くのに十分なものだった。それがきっかけで外の世界に思いを馳せるようになり、部族に残るという考えを覆して、成年後に故郷を離れることにしたのだという。
しかし始まりは一片の雪花だったとしても、いつしか分厚い雪に覆い尽くされてしまうものである。
故郷を離れたトターは気の合う友人に出会い、共に自分たちだけの傭兵団を立ち上げた。しっかりと訓練を積んだ戦闘員を多く擁する傭兵団は、段々と規模を大きくしていき、名も通るようになった。だが、何もかもが上手く進んでいる時に発生した事故によって、傭兵団はその構成員の半数を失ってしまった。トターもその一件で鉱石病に感染し、歩行能力をほぼ失ってしまったのだという。傭兵団と共に進めなくなった彼は森の奥に取り残された。雪境に近いその森は頻繁に吹雪に見舞われていた。晴れていたはずなのに、次の瞬間は予兆もなく、暴風が氷雪を携えて襲ってくるのだ。
トターは、傭兵団を抜けてから随分と長い間、かなり落ち込んでいたと吐露した。それが止まったのは、ある日痛み止めのせいで眠気に襲われていた時の出来事のおかげだった。窓を破らんと暴れる吹雪がウッドハウスの外で吹き荒れていたのが、いつしか収まり、辺りは静寂に包まれた。久々の日差しが彼の閉じた瞼に降り注ぎ、まとわりつく悪夢から彼を目覚めさせた。そして彼は窓の外を眺めた。無限に広がる真っ白な森に、数本の葉が落ちた真っ直ぐな杉の木が雲一つない空に突き刺さっていた。そんな景色の中から、トターは久々に落ち着いた気分を取り返すことができたのだという。置いていかれたことに苦しむことがようやくなくなり、自らに降りかかった不幸に対しても達観することができるようになったそうだ。
しかし会話の最中、トターはずっと下に目を向け、何度も唇を舐めていた。明らかに何か隠している反応だった。数度問い詰めたが、結局は明かしてくれず、会話にも拒絶の態度を見せ始めた。
そんなトターの反応は私に不安を覚えさせるものだった。積もった雪の下に覆い隠されたのは、彼の絶望と苦しみだけではないかもしれない。私はどうしても恐ろしい想像が思い浮かんでしまう。あの無垢な雪原を、あの極寒の冬を、彼は本当に抜け出せているのだろうか?
「もう少し薪をくべてくる。あんた、凍りつきそうだしな。」
あなたにお湯を渡したトターは、振り返って暖炉の火をいじった。バチバチと鳴る火が、暖炉の内側を真っ赤に照らしている。
「本艦からここまでどれくらい歩いたんだ?二キロ?それとも三キロくらいか?」
あなたは彼の質問に答えず、お湯の入ったコップにふうふうと息を吹きつけた。蒸気があたり、眉毛に固まった雪が溶けて滑稽にも顔から滴り落ちている。
「ついでとはいえ訪ねて来てくれてありがとな。ビーンスープでも飲むか?」暖炉の中に掛けられたスープの入ったジャーからコトコトと音が鳴り、あなたが答える前に彼は自分の分をよそって食べ始めた。品がある食べ様とは言い難く、さして噛みもせずに急いで飲み込んだ。
「心配する必要はない、俺は大丈夫だ。」そう慎重な口調で言った彼は、手の甲で口元を拭った。
「ここの冬はそれほど恐ろしいものじゃない……孤独を耐え忍んだ者は、寒さを恐れないさ。」
あなたにお湯を渡したトターは、振り返って暖炉の火をいじった。バチバチと鳴る火が、暖炉の内側を真っ赤に照らしている。
「本艦からここまでどれくらい歩いたんだ?二キロ?それとも三キロくらいか?」
あなたは彼の質問に答えず、お湯の入ったコップにふうふうと息を吹きつけた。蒸気があたり、眉毛に固まった雪が溶けて滑稽にも顔から滴り落ちている。
「ついでとはいえ訪ねて来てくれてありがとな。ビーンスープでも飲むか?」暖炉の中に掛けられたスープの入ったジャーからコトコトと音が鳴り、あなたが答える前に彼は自分の分をよそって食べ始めた。品がある食べ様とは言い難く、さして噛みもせずに急いで飲み込んだ。
「心配する必要はない、俺は大丈夫だ。」そう慎重な口調で言った彼は、手の甲で口元を拭った。
「ここの冬はそれほど恐ろしいものじゃない……孤独を耐え忍んだ者は、寒さを恐れないさ。」
HP
1550
攻撃力
970
防御力
145
術耐性
0
配置コスト
22
攻撃間隔
2.4 秒
ブロック数
1
再配置時間
70 秒
素質
- 鋭い眼光ステルス状態の敵を攻撃することができ、攻撃範囲内にステルス状態の敵がいる場合、攻撃力+17%
スキル
設定で詳細一覧を有効にして、詳細データが表示されます。
 貫日の一射攻撃回復自動発動必要SP3次の通常攻撃時、攻撃対象数+1、攻撃対象に攻撃力の220%の物理ダメージを与えるatk_scale2.2max_target2
貫日の一射攻撃回復自動発動必要SP3次の通常攻撃時、攻撃対象数+1、攻撃対象に攻撃力の220%の物理ダメージを与えるatk_scale2.2max_target2 砕虹の勁弩自動回復手動発動初期SP25必要SP40継続時間30 秒攻撃速度+50、攻撃対象数+2、攻撃対象が1体のみの場合、その対象に攻撃力の225%の物理ダメージを与えるattack_speed50attack@s2c.atk_scale2.25attack@s2n.max_target3
砕虹の勁弩自動回復手動発動初期SP25必要SP40継続時間30 秒攻撃速度+50、攻撃対象数+2、攻撃対象が1体のみの場合、その対象に攻撃力の225%の物理ダメージを与えるattack_speed50attack@s2c.atk_scale2.25attack@s2n.max_target3
モジュール
 ORIGINALトターの記章
ORIGINALトターの記章 トターは距離を保って火力で大型の敵を制圧することに秀でている。
トターは距離を保って火力で大型の敵を制圧することに秀でている。
外勤部門の決定に基づき
外勤任務においては狙撃オペレーターとして区分し、破城射手の責務を担う。
特別に本記章を授与し、
その証明とする。 SIE-Xスノードーム
SIE-XスノードームSTAGE ステータス 強化説明 1 - 攻撃力 +35
- 防御力 +15
破城射手の特性 重量が最も重い敵を優先して攻撃重量ランクが3以上の敵を攻撃時、攻撃力が115%まで上昇2 - 攻撃力 +47
- 防御力 +25
鋭い眼光 ステルス状態の敵を攻撃でき、攻撃範囲内にステルス状態の敵がいる場合、攻撃力+22%3 - 攻撃力 +55
- 防御力 +30
鋭い眼光 ステルス状態の敵を攻撃でき、攻撃範囲内にステルス状態の敵がいる場合、攻撃力+27% 「やはりここを出るべきだな、俺は。」
「やはりここを出るべきだな、俺は。」
うつむいて麻縄で矢じりを縛りつつ、男は一人呟いた。
「数日前通りかかった傭兵隊が狙撃手を探していたはずだ……俺ならうってつけだろう。」
「広大な砂漠を越えて、鬱蒼とした森を抜ければ、北方の都市にたどり着く。」
「その都市には雪が降るらしい。冬になると、どんなに着込んでも凍えるほどに寒いとか。」
「そこでなら新しい友もできるだろうし、金を貯めて大きな家を買うことも、伴侶を見つけることもできるはずだ。」
「今いるここは、俺の居場所じゃない。とにかく暑いしみんないつも汗だくだし……」
「生活だってつまらない。毎日、動物の後を追うぐらいしかやることがないくらいだ。」
「俺のやるべきことはもっとほかにあるはず――そうだろう?」
矢を手にして幾度か振り、矢じりがきちんと固定されているのを確認すると、男はそれを弓につがえた。
その矢は、肉眼では捉えられぬほど遠くへと放たれて消えていった。
「ここを出たほうがいいぞ、あんた。」
その言葉に、男はうつむいたまま何も答えなかった。
斧が何度か振り下ろされ、薪の山ができあがっていく。
「数日後にこの辺りを通る傭兵隊は狙撃手を探しているらしい……あんたならうってつけだろう。」
「広大な森林を越えて、波打つ麦畑を抜ければ、南方の町にたどり着く。」
「その町は雪など滅多に降らないらしい。冬でも着込む必要はないし、木々も青々としているとか。」
「そこでなら新しい友もできるだろうし、金を貯めることも、余生を一緒に過ごしてくれる女を見つけることもできるはずだ。」
「今いるここは、あんたの居場所じゃない。とにかく寒いし冬は吹雪いてばかりだし……」
「周りを見渡してみろ。人家もほとんどないこの荒れ地じゃ、狩りをするほか楽しみなんてない。」
「あんたのやるべきことはもっとほかにあるはず――そうだろう?」
男は斧を軽く振るうと、薪の山の上にそっと置いた。
そして、なおも黙り込んだまま、ただ唇をかんでいた。
しばらくするうちに口の中には鉄の味が広がっていく。
やがて、男はこう答えた。
「いいや、ここがいい。俺はここに残るべきなんだ。」
「残ってどうするつもりだ?」
「待つのさ。」
「待つって何を?」
男はその答えがわからず、再び口をつぐんだ。
自分が待っているのは、吹雪の終わりだろうか。あるいは雪解けだろうか。
もしかすると、少年時代に放った矢が時を越え、あの頃の無知な勇気と無邪気な誓いを乗せたまま、騙し騙し生きている現状を打ち砕いて心臓に突き刺さるのを待っているだけかもしれない。
そうなれば、彼の心は一度砕かれ、再び輝き出して温もりを取り戻すことだろう。
基地スキル
 霞む視界製造所配置時、製造効率+30%、自身の体力減少分が4ごとに、製造効率-5%
霞む視界製造所配置時、製造効率+30%、自身の体力減少分が4ごとに、製造効率-5% 窓外の吹雪
窓外の吹雪 製造所配置時、自身の体力減少分が12を上回る時、製造効率+10%、保管上限+6
製造所配置時、自身の体力減少分が12を上回る時、製造効率+10%、保管上限+6