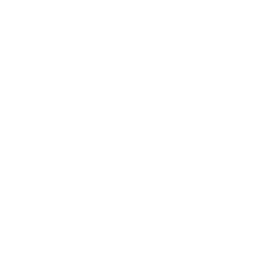
- Akafuyu
- 赤冬
- 아카후유
アカフユ
前衛タイプ — 武者
味方の治療対象にならない
敵を攻撃する度自身のHPを70回復
敵を攻撃する度自身のHPを70回復
- HK04
- 近距離
- 生存
- 火力
ボーナスを含む
HP
3635
攻撃力
758
防御力
383
術耐性
0
配置コスト
25
攻撃間隔
1.2 秒
ブロック数
1
再配置時間
70 秒
素質
- 信影流・羽飛配置中、最大で攻撃速度+100の不屈状態を獲得する(HPが最大値の70%減少時、効果最大)
スキル
設定で詳細一覧を有効にして、詳細データが表示されます。
 信影流・雷刀之勢自動回復手動発動必要SP16継続時間12 秒ブロック数が0になり、攻撃力+80%、通常攻撃が2連撃になるatk0.8
信影流・雷刀之勢自動回復手動発動必要SP16継続時間12 秒ブロック数が0になり、攻撃力+80%、通常攻撃が2連撃になるatk0.8 信影流・十文字勝自動回復手動発動初期SP15必要SP25継続時間20 秒HPが現在値の50%減少し、シールドを1枚獲得(スキル効果時間終了後消失)、攻撃力+100%、防御力+120%atk1def1.2hp_ratio0.5
信影流・十文字勝自動回復手動発動初期SP15必要SP25継続時間20 秒HPが現在値の50%減少し、シールドを1枚獲得(スキル効果時間終了後消失)、攻撃力+100%、防御力+120%atk1def1.2hp_ratio0.5
モジュール
 ORIGINALアカフユの記章
ORIGINALアカフユの記章 SBL-X武将の甲冑
SBL-X武将の甲冑STAGE ステータス 強化説明 1 - 攻撃力 +55
- 防御力 +30
武者の特性 味方の治療対象にならない
敵を攻撃する度自身のHPを70回復HPが50%未満の時、25%の加護状態を獲得2 - 攻撃力 +65
- 防御力 +42
信影流・逆風 敵をブロックしている時、防御力+8%3 - 攻撃力 +70
- 防御力 +50
信影流・逆風 敵をブロックしている時防御力+12%
基地スキル
 前衛エキスパートα訓練室で協力者として配置時、前衛の訓練速度+30%
前衛エキスパートα訓練室で協力者として配置時、前衛の訓練速度+30% 信影流
信影流 訓練室で協力者として配置時、前衛の訓練速度+30%。特化ランク1への訓練をサポートする場合、訓練速度がさらに+45%
訓練室で協力者として配置時、前衛の訓練速度+30%。特化ランク1への訓練をサポートする場合、訓練速度がさらに+45%

