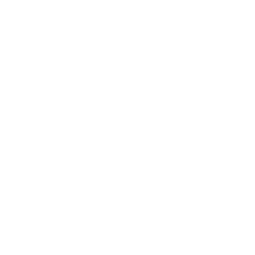
- Santalla
- 寒檀
- 산탈라
サンタラ
術師タイプ — 拡散術師
敵に範囲術ダメージを与える
- SI02
- 遠距離
- 範囲攻撃
- 牽制
ボーナスを含む
【コードネーム】サンタラ
【性別】女
【戦闘経験】七年
【出身地】サーミ
【誕生日】3月19日
【種族】フェリーン
【身長】170cm
【鉱石病感染状況】
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。
【性別】女
【戦闘経験】七年
【出身地】サーミ
【誕生日】3月19日
【種族】フェリーン
【身長】170cm
【鉱石病感染状況】
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。
【物理強度】標準
【戦場機動】標準
【生理的耐性】優秀
【戦術立案】標準
【戦闘技術】標準
【アーツ適性】優秀
【戦場機動】標準
【生理的耐性】優秀
【戦術立案】標準
【戦闘技術】標準
【アーツ適性】優秀
わけあって自らを部族から追放したサーミのシャーマン。鉱石病の症状が落ち着いてからはロドスを新たに所属する部族とみなし、新しい生活を手に入れた。
風雪を操ることに長け、極寒の状況下や極めて視界の悪い嵐の中でも自在に動くことができる。そのため、サーミを深く知らない敵からは「魔女」と呼ばれ恐れられているようだ。
風雪を操ることに長け、極寒の状況下や極めて視界の悪い嵐の中でも自在に動くことができる。そのため、サーミを深く知らない敵からは「魔女」と呼ばれ恐れられているようだ。
造影検査の結果、臓器の輪郭は不明瞭で異常陰影も認められる。循環器系源石顆粒検査の結果に異常があり、鉱石病の兆候が認められる。以上の結果から、鉱石病感染者と判定。
【源石融合率】10%
左目が著しく病変し、完全に結晶化しているが、該当器官は今も機能している。
【血液中源石密度】0.16u/L
鉱石病感染後一定期間が経過しているため、楽観視はできない状況。だが幸いにして、近頃は治療に非常に協力的であるため、症状は安定しつつある。
「彼女、結晶化した目のほうもまだ見えてるって言ったわよね?」
――匿名医療オペレーター
【源石融合率】10%
左目が著しく病変し、完全に結晶化しているが、該当器官は今も機能している。
【血液中源石密度】0.16u/L
鉱石病感染後一定期間が経過しているため、楽観視はできない状況。だが幸いにして、近頃は治療に非常に協力的であるため、症状は安定しつつある。
「彼女、結晶化した目のほうもまだ見えてるって言ったわよね?」
――匿名医療オペレーター
サンタラは鋼鉄に囲まれて暮らすよりも、木々や石に囲まれて自然と共に歩むことを好むため、ロドスには滅多に現れない。それゆえ平素はサーミで活動しており、外勤任務や、初めてサーミを訪れるオペレーターの案内役、サーミの鉱石病患者が治療のためにロドス本艦へ向かう際の護衛などを務めている。これは、サーミ出身のオペレーターがサーミで仕事をしているというだけの、至って普通のことなのだが……人事部の統計によると、地元で働きたがる人々を出身地域ごとに統計化した時、サーミの出身者たちはこの割合が群を抜いて高いらしい。ただ、これはサーミ人の一部――特に中北部出身の者に共通する傾向だと指摘する者もいる。なんでも、彼らはサーミの自然環境から離れた途端、全身に不快感を覚えるのだそうだ。しかし、そう感じてしまうのもある意味仕方のないことだろう。サーミとそれ以外の地域の文化を比較した時、その共通点は極めて少ない。加えて、サーミ人が外と接触する機会というのは、ウルサスやクルビアとの取引くらいのものだ。そのため、初めて外の環境に触れ、今まで培った常識が完全に通用しないと知った彼らが、サーミに帰りたくなるのは自然なことである。サンタラもそれをよく理解しているため、本艦への滞在中はいつも、子供たちに交じって授業を受けている。ほかの子供らが学んだ内容をノートに書き記している間、サンタラはその隣で木板を懸命に彫っている。彼女は口数が少ないため、静かで穏やかな印象を持たれがちだが、実際にはサーミ訛りが引き起こし得るトラブルを回避しようとしているだけだ。あるいは他人と会話する際に、訛りが混じることを好ましく思っていないとも言える。サンタラの価値観において、訛りがあることはその言語を尊重していない意味になるらしい。ゆえに背負った重荷を降ろし、心の赴くままに話す彼女を見たことのある幸運な者はかなり限られている。そして、そんな時でも、サンタラは依然思いやりと優しさに溢れた語り手兼聞き手となるため、ロドスに来たばかりの頃、まだオペレーターになる前の彼女がどれほど偏屈だったかを知る者は、さらに限られてくるだろう。
サーミとウルサスの国境付近に出没し、ウルサス政府を悩ませてやまない「魔女」の正体がサンタラであることを知る者はほとんどいない。彼女はかつて、源石が自身の体にもたらす被害も忘れ、半狂乱の状態でなりふり構わずウルサス人を襲っていた。サーミで外勤任務にあたっていたロドスのオペレーターが、偶然氷原でサンタラを発見した時には、彼女が意識を失い倒れてからすでにかなりの時間が経過していたという。
よそ者に助けられるなど、サンタラにとってはまったくの予想外だったようだ。しかし実際にそれが起きたからには、その事実を認めるしかない。そこでサンタラは恩返しとして、無条件に相手の要求を何でも一つ聞くことを約束した。すると、そのよそ者――ロドスのオペレーターは、自分と共にサーミを離れ、ロドスで鉱石病の治療を受けてほしいと言ったのだ。
サンタラはサーミを離れたこともなければ、サーミの外に詳しくもなかった。その時は反射的に断ったものの、先に約束をしてしまったため、結局彼女は渋々そのオペレーターと共に巨大な鋼の船に乗る羽目になった。
ロドスに来たばかりの頃、サンタラは新しい生活にまるで馴染めずにいた。巨大な鋼鉄の中で暮らすのに慣れていなかったことはもちろん、至る所で見かけるウルサス人に対して本能的に脅威を感じてしまうことも理由のひとつである。サンタラの故郷はウルサスの侵略によって滅ぼされたにもかかわらず、ここにいるウルサス人たちは何事もなかったかのように挨拶をしてくるのだ。治療を開始した初日に、ロドスの艦内ではウルサス人に手出ししないと誓いを立てていなければ、彼女はきっととうに襲い掛かっていただろう。
だが、冷たい鋼鉄に囲まれたその中で、再び友情と信頼の温かさに触れることができたのは、サンタラ自身にも意外なことだった。ウルサス人の残忍さと、差別的な眼差しを向けてくる観光客がもたらした偏見によって、彼女の心にはサーミ以外のすべてに対する拒絶が植え付けられていた。だが、その偏見を隅へと追いやり、真の意味で理性的にロドスの人々に接した時、サンタラは彼らと自分の間には何の違いもないということに気付いた。皆同じように病に苦しめられ、息詰まる日々の中をもがきながら生きているのだ。それなのに、ただ理解できないから、したくないからという理由で他人を感情の捌け口にしたり、自身の苦痛を他人にまで強いるような狭量で自分勝手な心の在り方は、サーミフィヨドとしても、シャーマンとしてもあってはならないものだと彼女は考えた。
そのため、サンタラは偏見も恨みもいったん捨て置き、自分を変えようと試みた。そんな彼女の努力を見守ってきた友人たちは、タイミングを見計らって、前々から準備していた特製の衣装をサンタラにプレゼントした。そうして彼女は少しずつ、我々がよく知る今の姿へと変わっていったのだ。
よそ者に助けられるなど、サンタラにとってはまったくの予想外だったようだ。しかし実際にそれが起きたからには、その事実を認めるしかない。そこでサンタラは恩返しとして、無条件に相手の要求を何でも一つ聞くことを約束した。すると、そのよそ者――ロドスのオペレーターは、自分と共にサーミを離れ、ロドスで鉱石病の治療を受けてほしいと言ったのだ。
サンタラはサーミを離れたこともなければ、サーミの外に詳しくもなかった。その時は反射的に断ったものの、先に約束をしてしまったため、結局彼女は渋々そのオペレーターと共に巨大な鋼の船に乗る羽目になった。
ロドスに来たばかりの頃、サンタラは新しい生活にまるで馴染めずにいた。巨大な鋼鉄の中で暮らすのに慣れていなかったことはもちろん、至る所で見かけるウルサス人に対して本能的に脅威を感じてしまうことも理由のひとつである。サンタラの故郷はウルサスの侵略によって滅ぼされたにもかかわらず、ここにいるウルサス人たちは何事もなかったかのように挨拶をしてくるのだ。治療を開始した初日に、ロドスの艦内ではウルサス人に手出ししないと誓いを立てていなければ、彼女はきっととうに襲い掛かっていただろう。
だが、冷たい鋼鉄に囲まれたその中で、再び友情と信頼の温かさに触れることができたのは、サンタラ自身にも意外なことだった。ウルサス人の残忍さと、差別的な眼差しを向けてくる観光客がもたらした偏見によって、彼女の心にはサーミ以外のすべてに対する拒絶が植え付けられていた。だが、その偏見を隅へと追いやり、真の意味で理性的にロドスの人々に接した時、サンタラは彼らと自分の間には何の違いもないということに気付いた。皆同じように病に苦しめられ、息詰まる日々の中をもがきながら生きているのだ。それなのに、ただ理解できないから、したくないからという理由で他人を感情の捌け口にしたり、自身の苦痛を他人にまで強いるような狭量で自分勝手な心の在り方は、サーミフィヨドとしても、シャーマンとしてもあってはならないものだと彼女は考えた。
そのため、サンタラは偏見も恨みもいったん捨て置き、自分を変えようと試みた。そんな彼女の努力を見守ってきた友人たちは、タイミングを見計らって、前々から準備していた特製の衣装をサンタラにプレゼントした。そうして彼女は少しずつ、我々がよく知る今の姿へと変わっていったのだ。
サンタラの一族は「亡寒」の部族と呼ばれており、彼らはかつてサーミとウルサスの国境付近――氷原の入り口近くに位置する森に暮らしていた。環境の過酷さを理由に、部族には子捨ての風習があり、サンタラは本来なら捨てられ獣の餌となる運命だった。しかし、いざ捨てられかけた時、偶然にも部族の老樹の枝が風に吹かれてなびき、まだ赤子だった彼女をくるんでいた布に引っ掛かったのだ。そうして、定められたはずの死の運命は、死せる古木によって変えられた。部族の者たちはその偶然をサーミの意志とみなし、サンタラは再び両親の元に戻され育てられることとなった。サンタラの両親が狩りの最中に命を落とした後は、部族の雪祭司が自らの手で彼女を成人まで育て上げ、部族のシャーマンとしてのしきたりやアーツをすべて彼女に伝授したという。ゆえにサンタラはいずれ新たな雪祭司に、そして部族の長になるのだと、当時は誰もがそう信じていた。
だが、何事もそう上手くいかないのが世の常である。北からの吹雪は絶えず森を飲み込んでおり、この地で暮らし続けようとすれば、部族全体が滅び去るだろうという時が来たのだ。しかし、仮に族樹から離れれば、彼らはほかの部族の笑いものになってしまう。苦悩の末最終的に部族は二分され、片方は生存に適した森を探しに南へと移り、残りの者はその場に留まって、老樹が本当の最期を迎える時まで見守ることにした。
結局ほとんどの者は信仰よりも命を優先し、雪祭司に率いられ老樹を離れていった。当時残ったのはサンタラと数十人の敬虔な信者のみだったという。吹雪は瞬く間に森のすべてを破壊して、残されたものはついに老樹だけとなった。人々は老樹を囲むように野営地を立て、サンタラは自身のアーツで吹雪の進路を操り、最も荒れ狂う暴風をほかの場所へと誘導することで老樹の安全を確保した。サンタラの命はこの老樹から始まっており、ゆえに彼女には、老樹のために命を捧げる覚悟がとうにできていたのだ。彼女はありとあらゆる可能性を想定していたが、それでも突然現れたウルサス人が、この地はウルサスの領土だと一方的に宣言してくることまでは予想できなかった。彼らを相手に誰もがそこを離れようとせず、屈することを拒んだために命を落とし――運よく難を逃れたのは、見回りに出ていたサンタラだけだった。その後、ウルサスの国境警備隊が彼女を捕えるべく罠を仕掛けていた時、サンタラは荒れ狂う吹雪を呼び寄せてそのすべてを飲み込ませた。ウルサスが自らの同胞を屠るのなら、自然をもってウルサスを屠ろうというのだ。しかしその吹雪の中、自暴自棄になったウルサス兵が源石の棘でサンタラの目を貫いた。鉱石病の呪いと苦痛を彼女に与えようとしたのである。けれどサンタラにとって、それは無限に燃え盛る怒りの炎へわらの束を投げ込まれただけのことだった。以来、サンタラはウルサスの国境付近を彷徨い、視界に入ったウルサス人を手あたり次第に狩りつくした。そのため彼女はウルサス人から「魔女」と呼ばれるようになり、高額な懸賞金をかけられたのだ。
今に至っても、彼女の憎しみは融けることなくそこにある。
だが、何事もそう上手くいかないのが世の常である。北からの吹雪は絶えず森を飲み込んでおり、この地で暮らし続けようとすれば、部族全体が滅び去るだろうという時が来たのだ。しかし、仮に族樹から離れれば、彼らはほかの部族の笑いものになってしまう。苦悩の末最終的に部族は二分され、片方は生存に適した森を探しに南へと移り、残りの者はその場に留まって、老樹が本当の最期を迎える時まで見守ることにした。
結局ほとんどの者は信仰よりも命を優先し、雪祭司に率いられ老樹を離れていった。当時残ったのはサンタラと数十人の敬虔な信者のみだったという。吹雪は瞬く間に森のすべてを破壊して、残されたものはついに老樹だけとなった。人々は老樹を囲むように野営地を立て、サンタラは自身のアーツで吹雪の進路を操り、最も荒れ狂う暴風をほかの場所へと誘導することで老樹の安全を確保した。サンタラの命はこの老樹から始まっており、ゆえに彼女には、老樹のために命を捧げる覚悟がとうにできていたのだ。彼女はありとあらゆる可能性を想定していたが、それでも突然現れたウルサス人が、この地はウルサスの領土だと一方的に宣言してくることまでは予想できなかった。彼らを相手に誰もがそこを離れようとせず、屈することを拒んだために命を落とし――運よく難を逃れたのは、見回りに出ていたサンタラだけだった。その後、ウルサスの国境警備隊が彼女を捕えるべく罠を仕掛けていた時、サンタラは荒れ狂う吹雪を呼び寄せてそのすべてを飲み込ませた。ウルサスが自らの同胞を屠るのなら、自然をもってウルサスを屠ろうというのだ。しかしその吹雪の中、自暴自棄になったウルサス兵が源石の棘でサンタラの目を貫いた。鉱石病の呪いと苦痛を彼女に与えようとしたのである。けれどサンタラにとって、それは無限に燃え盛る怒りの炎へわらの束を投げ込まれただけのことだった。以来、サンタラはウルサスの国境付近を彷徨い、視界に入ったウルサス人を手あたり次第に狩りつくした。そのため彼女はウルサス人から「魔女」と呼ばれるようになり、高額な懸賞金をかけられたのだ。
今に至っても、彼女の憎しみは融けることなくそこにある。
サンタラはあまりにも多くの死を経験してきた。自分自身の、両親の、同じ部族の友人の、老樹の、そして仇敵の死を。
この先も、多くの死が待ち受けていることだろう。彼女は生まれながらに死と共にあるのだから。
サンタラはそれを否定したい、それに抗いたいと思っていたが、それはかなわぬ願いなのだろう。
憎しみに理性を飲まれた時などは、それが正しいとすら認めてしまいそうになる。
もし新しい友人たちの助けが、ロドスが存在しなければ……彼女は痛みの中で目覚めたあともきっと殺戮を繰り返し、狂気に染まり続けていただろう。そうして迎える最期はといえば、鉱石病の発作による死か、ウルサス政府の手に落ち処刑されるか、あるいは悪魔に侵食され「寒災」となり果てるか、だ。
サーミはあまりにも寒冷な土地であるため、そこにいたサンタラの心に残されたわずかばかりの温もりは、寒風に吹き消されてしまっていた。ゆえに彼女の心は冷たく凍てつき、冷ややかに他人をあしらうことしかできなくなってしまったのだ。
そのためサンタラは、アーミヤが微笑みと共に握手を求めてきた時や、そばにいた子供から単語の意味を尋ねられた時、また、誰かからはちみつよりも甘い飴を受け取った時……
そして再び誰かのために啓示を彫った時や、盃の酒を一気に飲み干した時、何の心配もなく安心して眠りについた時……
さらには、人生への情熱が凍てつく寒さを覆した時……そんな時に、ようやく理解したのだ。自身に纏わりついているものが死ではなく、過去であることを。
その過去も、命の温かさを感じるようなものだったはずだ。しかし残念なことに、光や熱は永遠にこの大地に留まれはしない。
ゆえにこそ、過去は記憶となり、符号となり、文字と紙の間に残されていくのだから。
本来それが留めおこうとしているのは、失う痛みや後悔ではない。むしろそれは、かつてあった日々の温かさと美しさを今に伝えるためにこそあるものなのだ。
そう理解したサンタラは、今後そのように行動していくことだろう。
なぜなら、過去は「今」でもあり、「未来」でもあるからだ。
この先も、多くの死が待ち受けていることだろう。彼女は生まれながらに死と共にあるのだから。
サンタラはそれを否定したい、それに抗いたいと思っていたが、それはかなわぬ願いなのだろう。
憎しみに理性を飲まれた時などは、それが正しいとすら認めてしまいそうになる。
もし新しい友人たちの助けが、ロドスが存在しなければ……彼女は痛みの中で目覚めたあともきっと殺戮を繰り返し、狂気に染まり続けていただろう。そうして迎える最期はといえば、鉱石病の発作による死か、ウルサス政府の手に落ち処刑されるか、あるいは悪魔に侵食され「寒災」となり果てるか、だ。
サーミはあまりにも寒冷な土地であるため、そこにいたサンタラの心に残されたわずかばかりの温もりは、寒風に吹き消されてしまっていた。ゆえに彼女の心は冷たく凍てつき、冷ややかに他人をあしらうことしかできなくなってしまったのだ。
そのためサンタラは、アーミヤが微笑みと共に握手を求めてきた時や、そばにいた子供から単語の意味を尋ねられた時、また、誰かからはちみつよりも甘い飴を受け取った時……
そして再び誰かのために啓示を彫った時や、盃の酒を一気に飲み干した時、何の心配もなく安心して眠りについた時……
さらには、人生への情熱が凍てつく寒さを覆した時……そんな時に、ようやく理解したのだ。自身に纏わりついているものが死ではなく、過去であることを。
その過去も、命の温かさを感じるようなものだったはずだ。しかし残念なことに、光や熱は永遠にこの大地に留まれはしない。
ゆえにこそ、過去は記憶となり、符号となり、文字と紙の間に残されていくのだから。
本来それが留めおこうとしているのは、失う痛みや後悔ではない。むしろそれは、かつてあった日々の温かさと美しさを今に伝えるためにこそあるものなのだ。
そう理解したサンタラは、今後そのように行動していくことだろう。
なぜなら、過去は「今」でもあり、「未来」でもあるからだ。
ウルサス人が与えた呪いは、サンタラの片目を結晶化させてしまった。
彼女は当初、目を貫いた源石の棘は、自身の命か、あるいは片目の視力を完全に奪うものだと思っていた。
だが、実際にはそのいずれも起こらなかった。
源石結晶が次第に集まって、新しい目となったからである。
無論、その目に映る大地は、もはや慣れ親しんだ姿ではなくなっていた。
命ある者も死せる者も、目に映るすべてが、単純な外見以外の情報を放出しているのが見えるからだ。
そしてそれは、いついかなる時もそうだった。
もともと、シャーマンになるための訓練を受けていたおかげで、サンタラは物事を外見と切り離して観察することができる。しかし、新たな目が可能とさせたのは、そうした包括的な観察ではなく――
ただ情報を受け取り続けることだった。
膨大で煩雑な、無数の情報を、否応なしにである。
ロドス医療部の最高責任者であるケルシーに相談したところ、彼女はサンタラにこの問題の解決方法を提示してくれた。
ケルシーいわく、そもそも源石は、ただ人体を破壊するまで無限に増殖するだけのものではない。
時には身体の器官と同化して、それを完全に結晶化させたうえで元の機能を保持させてこともあるのだという。だが、そうした変化はしばしば脳に極めて大きな負担を与えてしまうものなのだ。
そこで対処法として、二つの案が提示された。
一つは、定期的に注射を打つことでその力を無効化させるという案だ。この治療プロセス自体は、鉱石病の拡散を阻止及び抑制するための薬品投与と大差ないものである。
そしてもう一つは、アーツを用いて無秩序な情報の侵入を安定化させるという案だ。そうして脳、すなわち人体のデータ処理端末に、源石器官がもたらす余計な情報を無視し、フィルタリングして適応してもらう、というわけである。
最終的に、サンタラは後者を選んだ。
彼女は、この目が啓示板を、老樹を、悪魔を見た時に感じた――何かを掴めそうな感覚を覚えていた。
もし本当にサーミを、悪魔を、この大地すべてを理解できるとしたら……
サーミが直面している難局も、いとも容易く解決できるのだろうか?
源石の目は外部からの情報を受け入れ続けている。
しかし、その中に答えはなかった。
彼女は当初、目を貫いた源石の棘は、自身の命か、あるいは片目の視力を完全に奪うものだと思っていた。
だが、実際にはそのいずれも起こらなかった。
源石結晶が次第に集まって、新しい目となったからである。
無論、その目に映る大地は、もはや慣れ親しんだ姿ではなくなっていた。
命ある者も死せる者も、目に映るすべてが、単純な外見以外の情報を放出しているのが見えるからだ。
そしてそれは、いついかなる時もそうだった。
もともと、シャーマンになるための訓練を受けていたおかげで、サンタラは物事を外見と切り離して観察することができる。しかし、新たな目が可能とさせたのは、そうした包括的な観察ではなく――
ただ情報を受け取り続けることだった。
膨大で煩雑な、無数の情報を、否応なしにである。
ロドス医療部の最高責任者であるケルシーに相談したところ、彼女はサンタラにこの問題の解決方法を提示してくれた。
ケルシーいわく、そもそも源石は、ただ人体を破壊するまで無限に増殖するだけのものではない。
時には身体の器官と同化して、それを完全に結晶化させたうえで元の機能を保持させてこともあるのだという。だが、そうした変化はしばしば脳に極めて大きな負担を与えてしまうものなのだ。
そこで対処法として、二つの案が提示された。
一つは、定期的に注射を打つことでその力を無効化させるという案だ。この治療プロセス自体は、鉱石病の拡散を阻止及び抑制するための薬品投与と大差ないものである。
そしてもう一つは、アーツを用いて無秩序な情報の侵入を安定化させるという案だ。そうして脳、すなわち人体のデータ処理端末に、源石器官がもたらす余計な情報を無視し、フィルタリングして適応してもらう、というわけである。
最終的に、サンタラは後者を選んだ。
彼女は、この目が啓示板を、老樹を、悪魔を見た時に感じた――何かを掴めそうな感覚を覚えていた。
もし本当にサーミを、悪魔を、この大地すべてを理解できるとしたら……
サーミが直面している難局も、いとも容易く解決できるのだろうか?
源石の目は外部からの情報を受け入れ続けている。
しかし、その中に答えはなかった。
HP
1640
攻撃力
860
防御力
123
術耐性
20
配置コスト
33
攻撃間隔
2.9 秒
ブロック数
1
再配置時間
70 秒
素質
- 寒地の民配置から20秒後、攻撃力+15%、レジスト状態になる
スキル
設定で詳細一覧を有効にして、詳細データが表示されます。
 迅速攻撃γ自動回復手動発動初期SP15必要SP35継続時間35 秒攻撃力+45%、攻撃速度+45atk0.45attack_speed45
迅速攻撃γ自動回復手動発動初期SP15必要SP35継続時間35 秒攻撃力+45%、攻撃速度+45atk0.45attack_speed45 「魔女の涙」自動回復手動発動初期SP20必要SP40継続時間15 秒攻撃範囲拡大、攻撃間隔を超大幅に短縮、通常攻撃が攻撃範囲内のランダムなマスに氷柱を召喚する攻撃になる。地面に落ちた氷柱は周囲の敵全員に1秒の寒冷状態を付与すると同時に、攻撃力の90%の術ダメージを与えるbase_attack_time-2.4attack@cold1attack@atk_scale0.9
「魔女の涙」自動回復手動発動初期SP20必要SP40継続時間15 秒攻撃範囲拡大、攻撃間隔を超大幅に短縮、通常攻撃が攻撃範囲内のランダムなマスに氷柱を召喚する攻撃になる。地面に落ちた氷柱は周囲の敵全員に1秒の寒冷状態を付与すると同時に、攻撃力の90%の術ダメージを与えるbase_attack_time-2.4attack@cold1attack@atk_scale0.9
モジュール
 ORIGINALサンタラの記章
ORIGINALサンタラの記章 サンタラは複数の敵に対するアーツ攻撃に秀でている。
サンタラは複数の敵に対するアーツ攻撃に秀でている。
外勤部門の決定に基づき
外勤任務においては術師オペレーターとして区分し、拡散術師の責務を担う。
特別に本記章を授与し、
その証明とする。 SPC-Y「アイス・ブレイジャー」
SPC-Y「アイス・ブレイジャー」STAGE ステータス 強化説明 1 - 配置コスト -8
- HP +80
- 攻撃力 +40
拡散術師の特性 敵に範囲術ダメージを与える配置コスト減少2 - 配置コスト -8
- HP +125
- 攻撃力 +60
寒地の民 配置から15秒後、攻撃力+18%、レジスト状態になる3 - 配置コスト -8
- HP +155
- 攻撃力 +70
寒地の民 配置から15秒後、攻撃力+20%、自身がレジスト状態になる サンタラは炎が上がる酒を一気に飲み干すと、冷たい雪の結晶を伴う息を一つ吐く。
サンタラは炎が上がる酒を一気に飲み干すと、冷たい雪の結晶を伴う息を一つ吐く。
その中に滾る炎熱に、彼女はいささか驚きを隠せずにいた。
サーミにはこのようなものは存在しないのだ。
彼女がサーミを去ってからまだそれほど時間は経っておらず、ロドスの人々と特別親しくなったわけでもない。
急性の鉱石病を発症したことで休養が必要にならなければ、ここに留まることもなかっただろう。
ましてや、艦内のバーでスペシャルカクテルを味わうなど考えられないことだった。
そんな彼女の隣に、決して歓迎できない客が座った。ウルサス人の男性だ。
彼はサンタラをよそ者扱いすることなく、情熱的な挨拶をしてきた。
無論それは、サンタラからしてみれば、粗野なウルサス人の独り言に過ぎないのだが。
ロドスにいる時はこちらからウルサス人に手出ししないとは約束していたが、だからといって彼女には、ウルサス人に対する嫌悪感を隠すつもりもない。
それゆえに、周囲の気温は瞬時に数度下がった。
ウルサス人のほうも何かを察したようで、それ以上話しかけようとはせずにグレープジュースを注文し、そしてサンタラにもスペシャルカクテルを注文して寄越した。
しかし、彼女はそれを受け入れず――
バーテンダーがカクテルのグラスから手を離した瞬間、その燃えるカクテルは氷へ姿を変えてしまった。
ウルサス人はサンタラの前に置かれたカクテルを手にとると、なんとかそれを融かして飲める状態にしようとした。
けれど、それは難しいことだった。
隣にいるシャーマンが、絶えずグラスの中に固まった酒の温度を下げ続けているとなればなおさらだ。
偶然の出会いは、今や二人の力比べの場と化していた。
氷を融かさんとするウルサス人と、氷の中に閉じこもってしまったフェリーン。
二人の競い合いは、バーの常連客が皆店を出て、バーテンダーが閉店準備を始めてもなお続いていた。
見かねたバーテンダーは、二人を追い出して店を閉めるために、凍った酒の入ったグラスを取り上げ……
静かな戦いは、一度幕を下ろしたのである。
そこで、サンタラは何も言わずに立ち去ろうとしたが、「ウルサス人」は突然彼女を呼び止めた。
――その声は、サンタラがよく知るものだ。
それはロドスで初めてできた友人……とあるフェリーンのオペレーターの声だった。
サンタラが振り返ると、声の主は変装を解き、フェリーンの耳をあらわにした。
彼女は性別も、性格も、種族すらをも偽っていたのだ。
サンタラは彼女がこうしたことに長けているのを知ってはいたが、決して受け入れられない悪ふざけに感じた。
「あのお酒、私からなら受け取ってくれてたのかしら?」
そう聞くと、彼女はどこからともなくカクテルを取り出した。その表面には冷たく青い炎が揺れている。
「逆に言うと、私がウルサス人だったら、友達になることすらできなかったってこと?」
「へーえ、あなたってそういう人なのね、サンタラ。あの国から受けた苦しみを、ただ耳が丸いだけの知らない善人にもぶつけるつもりなの?」
サンタラは一瞬友人の無責任な悪ふざけを責めようとしたが、相手の湿った髪の毛を見て自分の行いを振り返り反論を呑み込んだ。
胸に滾る憎悪はそう易々と収まるものではないが、彼女は理性的な人間なのだ。
「一口どう?」と、フェリーンはカクテルを半分ほど喉に流してから、青色の炎を吐き出し、中身が半分残ったグラスをサンタラへと手渡す。
グラスを受け取ったサンタラは、それを一気に飲み干した。
彼女が再び口を開いたとき、鮮やかな炎が一瞬だけ宙を舞った。
基地スキル
 寒地生まれ宿舎配置時、自身以外のオペレーター1人の1時間ごとの体力回復量+0.55(同種の効果は高いほうのみ適応)。対象がサーミオペレーターの場合、更に+0.45
寒地生まれ宿舎配置時、自身以外のオペレーター1人の1時間ごとの体力回復量+0.55(同種の効果は高いほうのみ適応)。対象がサーミオペレーターの場合、更に+0.45 雪祭司候補
雪祭司候補 訓練室で協力者として配置時、基地に配置された(補佐を除く)サーミオペレーター1人につき、訓練速度+10%(最大3人まで)
訓練室で協力者として配置時、基地に配置された(補佐を除く)サーミオペレーター1人につき、訓練速度+10%(最大3人まで)