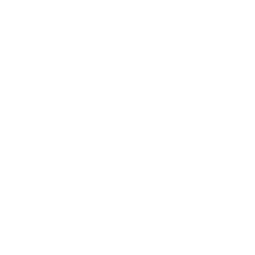
- Typhon
- 提丰
- 티폰
ティフォン
狙撃タイプ — 破城射手
重量が最も重い敵を優先して攻撃
- SI07
- 遠距離
- 火力
ボーナスを含む
【コードネーム】ティフォン
【性別】女
【戦闘経験】九年
【出身地】サーミ
【誕生日】2月1日
【種族】サルカズ
【身長】155cm
【鉱石病感染状況】
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。
【性別】女
【戦闘経験】九年
【出身地】サーミ
【誕生日】2月1日
【種族】サルカズ
【身長】155cm
【鉱石病感染状況】
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。
【物理強度】優秀
【戦場機動】標準
【生理的耐性】優秀
【戦術立案】普通
【戦闘技術】優秀
【アーツ適性】標準
【戦場機動】標準
【生理的耐性】優秀
【戦術立案】普通
【戦闘技術】優秀
【アーツ適性】標準
ティフォンはサーミで活動しているサルカズであり、狩人を自称している。彼女にはサーミの自然環境と潜在的な脅威に対する十分な知識と、対応技術がある。現在はオペレーター・マゼランの招待に応じてロドスと協力しており、サーミ及び果てなき氷原でのロドスの事務を支援している。
造影検査の結果、臓器の輪郭は不明瞭で異常陰影も認められる。循環器系源石顆粒検査の結果に異常があり、鉱石病の兆候が認められる。以上の結果から、鉱石病感染者と判定。
【源石融合率】3%
体表に極わずかな源石結晶の分布が見られる。
【血液中源石密度】0.19u/L
長期間荒野を駆け回っているにもかかわらず、ティフォンの感染状況はかなり安定している。恐らく、彼女にある程度全面的な防護手段を伝授した者がいるようだ。
それにしても、彼女が感染者だったとは……いや、本人が言う通り「サルカズが感染者なのは普通のこと」ではあるが、何でもないことのようにそう口にする彼女の姿に、医療部一同は複雑な気分にさせられた。
【源石融合率】3%
体表に極わずかな源石結晶の分布が見られる。
【血液中源石密度】0.19u/L
長期間荒野を駆け回っているにもかかわらず、ティフォンの感染状況はかなり安定している。恐らく、彼女にある程度全面的な防護手段を伝授した者がいるようだ。
それにしても、彼女が感染者だったとは……いや、本人が言う通り「サルカズが感染者なのは普通のこと」ではあるが、何でもないことのようにそう口にする彼女の姿に、医療部一同は複雑な気分にさせられた。
ロドスのオペレーターの中には、長期的に荒野で生活していた狩人も少なくない。だが、同じく狩人を名乗るティフォンは、これまで我々が接触してきたような、文明的集落から離れた放浪者とも、サーミの部族の中で狩猟により生計を立てている人間とも異なっている。ティフォン本人も自身の特殊性をある程度認識しているようだが、我々に対してはその具体的な要因を明確に説明することなく、再三にわたって自身の武器に触れるなと忠告するばかりだ。そのため、ロドスは彼女の問題点に的を絞った戦闘テストを行った。
ティフォンが弓矢と合わせて使用しているのは、極めて古典的なサルカズのアーツの一種である。彼女と同行するヴァラルクビンからも近しい系統のアーツを見せてもらったが、ヴァラルクビンのほうがそのアーツの本質をより明確に認識しており、一方ティフォンは主にアーツの特性を自身の矢の威力を高めることに用いているようだった。その後、我々はテストの記録の中に、極めて異常なデータをいくつか発見した。そこで、条件を制限したうえで繰り返し測定を行い、さらに現場の記録員が最終確認を行った結果、たとえアーツの補助がなくとも、その人目を惹く巨大な弓から放たれる矢そのものが、周りの空間にごくわずかな波動を発生させていることがわかった。それは肉眼ではほとんど捕えられないが、測定器は敏感にその異常を捕えていた。
その後の会話で知り得たことには、ティフォンは獣だけでなくサーミ人が「厄災」と呼ぶものも狩っており、部族の住民たちを手伝って「厄災」が引き起こす様々な異常現象への対応もしているとのことだった。「厄災」の行動ロジックはテラ大陸における一般的な生命体とは異なっているため、ティフォンも自然と常識から逸脱した戦闘手段を身に着けていたようだ。しかし、彼女によれば、それは我々からするとまったく馴染みのない異常現象に思えても、サーミにおいては戦う者なら誰もが必ず立ち向かうことになる敵の一つに過ぎないという。
「もっちろん、エンジニア部はあの子の武器に興味津々だよ。絶対触るなって何度も言ってくるもんだから、なおさら興味が湧いちゃうでしょ?だけどあの子、ほんとにしっかり見張っててさぁ。向こうがうたたねしてる間にこっそり休憩室に忍び込もうとしたら、真っ暗な中でいきなり足首掴まれて、本気で怖い思いしたよ!ほかにも、戦闘テストを受ける前に身体検査が必要だってウソついて、その隙に調べようともしたんだけど……ケルシーに後ろから肩を叩かれたのはそれよりもっと怖かったね!」
――クロージャ(エンジニア部による録音)
【権限記録】
オペレーター・ティフォンの武器に触れることは禁止されている。あの黒い外観の本質は、悪魔がもたらす現実空間への投影による物体の上書き、あるいはサーミ人が一般的に用いる呼称を使うのなら、「穢れ」と呼ばれるものだ。
この武器の特殊性と、彼女が用いるサルカズの古典的なアーツにより、ティフォンは悪魔がもたらす穢れを効果的に抑制することに成功している。ゆえに彼女による悪魔の撃退と、サーミの戦士たちによる抵抗は、本質的にまったく異なるものである。
ドクター。この警告は、これを確認できる人間のために記したものだ。インフィ氷原でこうした脅威に立ち向かう際に必要なのは、それを十分に理解し心の準備を整えることではなく、心の準備を整えてからそれを認識することだ。
――ケルシー
ティフォンが弓矢と合わせて使用しているのは、極めて古典的なサルカズのアーツの一種である。彼女と同行するヴァラルクビンからも近しい系統のアーツを見せてもらったが、ヴァラルクビンのほうがそのアーツの本質をより明確に認識しており、一方ティフォンは主にアーツの特性を自身の矢の威力を高めることに用いているようだった。その後、我々はテストの記録の中に、極めて異常なデータをいくつか発見した。そこで、条件を制限したうえで繰り返し測定を行い、さらに現場の記録員が最終確認を行った結果、たとえアーツの補助がなくとも、その人目を惹く巨大な弓から放たれる矢そのものが、周りの空間にごくわずかな波動を発生させていることがわかった。それは肉眼ではほとんど捕えられないが、測定器は敏感にその異常を捕えていた。
その後の会話で知り得たことには、ティフォンは獣だけでなくサーミ人が「厄災」と呼ぶものも狩っており、部族の住民たちを手伝って「厄災」が引き起こす様々な異常現象への対応もしているとのことだった。「厄災」の行動ロジックはテラ大陸における一般的な生命体とは異なっているため、ティフォンも自然と常識から逸脱した戦闘手段を身に着けていたようだ。しかし、彼女によれば、それは我々からするとまったく馴染みのない異常現象に思えても、サーミにおいては戦う者なら誰もが必ず立ち向かうことになる敵の一つに過ぎないという。
「もっちろん、エンジニア部はあの子の武器に興味津々だよ。絶対触るなって何度も言ってくるもんだから、なおさら興味が湧いちゃうでしょ?だけどあの子、ほんとにしっかり見張っててさぁ。向こうがうたたねしてる間にこっそり休憩室に忍び込もうとしたら、真っ暗な中でいきなり足首掴まれて、本気で怖い思いしたよ!ほかにも、戦闘テストを受ける前に身体検査が必要だってウソついて、その隙に調べようともしたんだけど……ケルシーに後ろから肩を叩かれたのはそれよりもっと怖かったね!」
――クロージャ(エンジニア部による録音)
【権限記録】
オペレーター・ティフォンの武器に触れることは禁止されている。あの黒い外観の本質は、悪魔がもたらす現実空間への投影による物体の上書き、あるいはサーミ人が一般的に用いる呼称を使うのなら、「穢れ」と呼ばれるものだ。
この武器の特殊性と、彼女が用いるサルカズの古典的なアーツにより、ティフォンは悪魔がもたらす穢れを効果的に抑制することに成功している。ゆえに彼女による悪魔の撃退と、サーミの戦士たちによる抵抗は、本質的にまったく異なるものである。
ドクター。この警告は、これを確認できる人間のために記したものだ。インフィ氷原でこうした脅威に立ち向かう際に必要なのは、それを十分に理解し心の準備を整えることではなく、心の準備を整えてからそれを認識することだ。
――ケルシー
我々はすでに探検隊からサーミについての物語を多く聞いているが、それはどうしてもサーミに対するある種の偏見に繋がり、かの地を後進的な未開の地だと認識させてしまう。たとえば、現地の人々が現代の科学技術を目の当たりにすれば、きっと初めて火を手に入れた原始人のように衝撃を受けるはずだという決めつけを抱くこと。そして、自然と科学技術を比較した時、我々は科学が自然に匹敵する力を与えてくれると考えるが、未だ自然を捨てきれない保守的な人々は科学の進歩に対する抵抗感を覚えるだろうと思い込むことなどがいい例だ。
カニパラートという前例のことを考慮し、サーミから新たな協力者を受け入れるにあたって、ロドスは特別な指導マニュアルを慎重に作成した。しかし、ティフォンがほかのオペレーター……彼女の言い方を借りるなら「南の人間」たちと交流をした際には、我々が想定していたような激しい文化的な衝突やすれ違いは一切生じなかった。――たとえば、彼女は先ほどふらりとここに入ってきて、電子ファイル内の二枚の写真を指し、位置を入れ替えたほうがいいとアドバイスを残して去っていった。つまり、それほどに慣れているということだ。
この要因として、クルビアがサーミにもたらした影響もあることは明らかだ。というのも、テラ大陸に存在する最先端技術の多くを、サーミ人はすでに目にしつつあるからである。とはいえ、クルビア人の観光と探検を中心とした開拓は、現状サーミ南部のごく一部の地域にまでしか及んでいない。ゆえに、自分から積極的に関わろうとしない限り、サーミ人がティフォンのようにこうしたものを使いこなすことはできないだろう。
もちろん、これはなにもティフォンが天才的な「現代文明」の学習者だからというわけではない。彼女はただ、少しばかりの好奇心と物事を幅広く知ろうとする信念をもって、目の前で起きたすべてを自然に受け入れたうえで、自身の今までの経験に即して理解しただけである。実際、積極的に外の人間と関わろうとする者こそあまりおらずとも、外界に対し「ありのまま受け入れる」態度を取るサーミ人自体は特段珍しくもない。クルビアのエンジニアたちは、しばしば自分たちがサーミ人に光をもたらしたのだと思いこんでいるが、サーミ人が科学技術に対して見せる喜びは、おいしい果物を拾った時のそれと大して変わりはしないだろう。
この話題について、ティフォンに意見を求めたところ、彼女は「すべては自然から生まれ育ったものだからな」と答えただけだった。
「本当、あの子の言うことはきちんと聞いたほうがいいよ。勝手なことをしたら、手をぶたれちゃうからね……実際やられたことあるけど、あれは相当痛かったな。おかげで、サーミ人がどんなに木々を尊敬してるかを繰り返し言い聞かされたあと一週間くらいは、療養庭園で剪定の手伝いをしててもビクビクしっぱなしだったよ。あの子と鉢合わせしないかって恐ろしくなっちゃってさ。」
「え、一週間しか怯えずに済んだ理由?それはね、一週間後にあの子も療養庭園の手伝いに来たからだよ、あははっ。」
「本人はその時、「この小さな南の土では、木はこのようにしか伸びられない。お前たちにこうした掟があるのなら仕方がないな。」なんて言ってたけど……しばらくして、その意味をようやく理解できたんだ。あの子は自分をサーミの主みたいに思ってるから、私たちがサーミに行った時は、現地の掟を教えてくれる。そして逆に、あの子がサーミを離れて他所を訪ねる時は、そちらの掟を学ばなくちゃいけないと思ってるんだよ。サーミの中でも、部族ごとに風習がちょっとずつ違っているみたいだし、それと同じことだろうね。あの子は、きっとそういう違いの間で暮らすことにすごく慣れてるんだよ。」
――サーミでの任務を担当した外勤オペレーター
カニパラートという前例のことを考慮し、サーミから新たな協力者を受け入れるにあたって、ロドスは特別な指導マニュアルを慎重に作成した。しかし、ティフォンがほかのオペレーター……彼女の言い方を借りるなら「南の人間」たちと交流をした際には、我々が想定していたような激しい文化的な衝突やすれ違いは一切生じなかった。――たとえば、彼女は先ほどふらりとここに入ってきて、電子ファイル内の二枚の写真を指し、位置を入れ替えたほうがいいとアドバイスを残して去っていった。つまり、それほどに慣れているということだ。
この要因として、クルビアがサーミにもたらした影響もあることは明らかだ。というのも、テラ大陸に存在する最先端技術の多くを、サーミ人はすでに目にしつつあるからである。とはいえ、クルビア人の観光と探検を中心とした開拓は、現状サーミ南部のごく一部の地域にまでしか及んでいない。ゆえに、自分から積極的に関わろうとしない限り、サーミ人がティフォンのようにこうしたものを使いこなすことはできないだろう。
もちろん、これはなにもティフォンが天才的な「現代文明」の学習者だからというわけではない。彼女はただ、少しばかりの好奇心と物事を幅広く知ろうとする信念をもって、目の前で起きたすべてを自然に受け入れたうえで、自身の今までの経験に即して理解しただけである。実際、積極的に外の人間と関わろうとする者こそあまりおらずとも、外界に対し「ありのまま受け入れる」態度を取るサーミ人自体は特段珍しくもない。クルビアのエンジニアたちは、しばしば自分たちがサーミ人に光をもたらしたのだと思いこんでいるが、サーミ人が科学技術に対して見せる喜びは、おいしい果物を拾った時のそれと大して変わりはしないだろう。
この話題について、ティフォンに意見を求めたところ、彼女は「すべては自然から生まれ育ったものだからな」と答えただけだった。
「本当、あの子の言うことはきちんと聞いたほうがいいよ。勝手なことをしたら、手をぶたれちゃうからね……実際やられたことあるけど、あれは相当痛かったな。おかげで、サーミ人がどんなに木々を尊敬してるかを繰り返し言い聞かされたあと一週間くらいは、療養庭園で剪定の手伝いをしててもビクビクしっぱなしだったよ。あの子と鉢合わせしないかって恐ろしくなっちゃってさ。」
「え、一週間しか怯えずに済んだ理由?それはね、一週間後にあの子も療養庭園の手伝いに来たからだよ、あははっ。」
「本人はその時、「この小さな南の土では、木はこのようにしか伸びられない。お前たちにこうした掟があるのなら仕方がないな。」なんて言ってたけど……しばらくして、その意味をようやく理解できたんだ。あの子は自分をサーミの主みたいに思ってるから、私たちがサーミに行った時は、現地の掟を教えてくれる。そして逆に、あの子がサーミを離れて他所を訪ねる時は、そちらの掟を学ばなくちゃいけないと思ってるんだよ。サーミの中でも、部族ごとに風習がちょっとずつ違っているみたいだし、それと同じことだろうね。あの子は、きっとそういう違いの間で暮らすことにすごく慣れてるんだよ。」
――サーミでの任務を担当した外勤オペレーター
ティフォンの習慣の多くは、明らかに育ての親であるヴァラルクビンの影響を受けている。彼女からはアーツの使い方を教わっただけでなく、すべての知識と情報を広く追い求めるその姿勢にも影響されたことで、ティフォン自身も新しい物事には自然と好奇心を抱くようになったようだ。また、ヴァラルクビンの運命への予見と理解を常に見聞きしてきたため、時折、ティフォンは極めて緊迫した状況において、その年齢にそぐわないほど達観した冷静さを見せることがある。
しかし、二人の関係は我々が想像しているほど親密ではないらしい。少なくとも、ティフォンの話では、実際のところ彼女がヴァラルクビンと共に過ごした時間はそれほど多くないという。それは、ヴァラルクビンがティフォンの育ての親となった時、すでにティフォンにはある程度の生存能力と戦闘能力が備わっていたからかもしれない。ティフォンの記憶の限りでは、ヴァラルクビンはいつも出かけており、どこに行くのか伝えていったことも一度もないらしい。ゆえにティフォンは闇の中でひとり、サイクロプスの岩窟の構造を手探りで理解し、自力で出口を見つけてサーミの荒野へと戻っていったという話だ。
狩人にとっては、サーミの自然そのものが己の帰る場所であり、サイクロプスの洞窟は彼女が見つけた隠れ家の一つでしかないようだ。そのため、ティフォンはヴァラルクビンの住む場所を普段「家」とは呼んでおらず、ヴァラルクビンに対してその本名以外の呼び名を用いることもない。ティフォンは、来る日も来る日も至る所に危険が潜む凍原と戦い続け、実践の中で生存のための知識と狩りの技術、そして大小様々な疑問を積み重ねてきた。彼女がその疑問を抱いて洞窟に戻った時、運よくヴァラルクビンがそこにいれば、ティフォンはこの博学なサイクロプスから辛抱強く事細かな回答を得ることができるのだ。
「わたしがロドスへ来て、お前たちに協力していることなら、彼女ももちろん知っているぞ。それどころか、道中でマゼランとわたしの乗っていた乗り物が、暴走した岩角獣と衝突して横転することも、物好きなクルビア人に撮影をせがまれることも事前に教えてくれたしな。彼女の警告のおかげで、どのトラブルも容易く解決できたんだ。普段はあそこまで色々言ってこないから、今回はわたしのことを心配してくれていたのだろう。」
「ん……?彼女が心配してくれたことが意外なのか?一緒にロドスへ来なかったから……?だが、心配をすることと、同行するかどうかは別の話だろう。」
「彼女には守るべき予言があり、そこにお前たちが深入りする必要はない。単に慣れればいいだけだ。」
しかし、二人の関係は我々が想像しているほど親密ではないらしい。少なくとも、ティフォンの話では、実際のところ彼女がヴァラルクビンと共に過ごした時間はそれほど多くないという。それは、ヴァラルクビンがティフォンの育ての親となった時、すでにティフォンにはある程度の生存能力と戦闘能力が備わっていたからかもしれない。ティフォンの記憶の限りでは、ヴァラルクビンはいつも出かけており、どこに行くのか伝えていったことも一度もないらしい。ゆえにティフォンは闇の中でひとり、サイクロプスの岩窟の構造を手探りで理解し、自力で出口を見つけてサーミの荒野へと戻っていったという話だ。
狩人にとっては、サーミの自然そのものが己の帰る場所であり、サイクロプスの洞窟は彼女が見つけた隠れ家の一つでしかないようだ。そのため、ティフォンはヴァラルクビンの住む場所を普段「家」とは呼んでおらず、ヴァラルクビンに対してその本名以外の呼び名を用いることもない。ティフォンは、来る日も来る日も至る所に危険が潜む凍原と戦い続け、実践の中で生存のための知識と狩りの技術、そして大小様々な疑問を積み重ねてきた。彼女がその疑問を抱いて洞窟に戻った時、運よくヴァラルクビンがそこにいれば、ティフォンはこの博学なサイクロプスから辛抱強く事細かな回答を得ることができるのだ。
「わたしがロドスへ来て、お前たちに協力していることなら、彼女ももちろん知っているぞ。それどころか、道中でマゼランとわたしの乗っていた乗り物が、暴走した岩角獣と衝突して横転することも、物好きなクルビア人に撮影をせがまれることも事前に教えてくれたしな。彼女の警告のおかげで、どのトラブルも容易く解決できたんだ。普段はあそこまで色々言ってこないから、今回はわたしのことを心配してくれていたのだろう。」
「ん……?彼女が心配してくれたことが意外なのか?一緒にロドスへ来なかったから……?だが、心配をすることと、同行するかどうかは別の話だろう。」
「彼女には守るべき予言があり、そこにお前たちが深入りする必要はない。単に慣れればいいだけだ。」
物好きな年長者たちがティフォンから根掘り葉掘り聞き出していなければ、彼女の幼少期の記憶がほとんど空白であることに気付くのは困難だっただろう。ティフォンは、ヴァラルクビンが育ての親であることは知っているものの、実の両親がどんな人で、どんな見た目をしていたのかすら知らないようだ。しかし、ある襲撃を受けるまで、二人と一緒に暮らしていたことだけは確信しているという。彼女の記憶によれば、両親と暮らしていた小屋は、サーミの部族から遠く離れた森の中にひっそり立っていたらしい。小屋の中にはいつも暖炉に火が灯っており、その明かりが壁にぼんやりとした二つの影を映し出していて……ティフォンは片隅に座り、その心温まる光景を見つめていたそうだ。彼女がそれ以外に知っていることは、目が覚めたあとにヴァラルクビンから聞かされたことばかりである。たとえば、いつもつけている角飾りと巨大な弓は、どちらも両親の形見らしい。ヴァラルクビンが彼女を助け出した時、穢されているその武器を処分すべきだと考えていたのだが、気絶したティフォンがそれをきつく抱きしめて何がなんでも離さなかったという話だ。
ティフォンは今でも、時折同じ内容の悪夢を見ることがある。その夢の中で、彼女は様々な種類のか弱く小さい獣となり、視界に収まり切れないほど大きな影に狩られてしまうのだ。自身の巣が壊され、親族が骨だけにされる光景は何度も何度も見てきたという。我々は始め、現代医学の視点から分析を行い、ティフォンの記憶喪失はトラウマによって自身の記憶を一部封じてしまったことが原因であると考えて、彼女と話し合ってみた。すると、両親に対しおぼろげながらも恋しさを抱いていたティフォンは、記憶を取り戻すことに前向きな反応を示し、トラウマを掘り起こすことによる苦痛も恐れていないと述べた。そこで、彼女の同意を得て、我々はティフォンに初歩的な検査を行った。しかし残念なことに、結果として、ティフォンは解離性健忘症でもなければ、脳へのダメージによって記憶機能が損なわれたというよく見られるパターンでもなかった。「厄災」がもたらす何らかのダメージは、現存の医学機材で捉えられるものではないと、そう結論付けてほぼ間違いないだろう。その後、ケルシー医師の要請があり、我々はティフォンに対するさらなる調査を中止した。
いずれにせよ、ティフォンは今のところ元気に暮らしており、自分の記憶喪失を異常だと思ったこともない。彼女はただ、忘れてしまった両親の温もりを恋しく感じているだけだ。テラ大陸における大多数の地域での死生観とは異なり、サーミ人は死者となることを、ただ身体という器が動かなくなっただけと捉えている。そして、儀式を一通り行えば、魂は自由にこの世を漂うことができ、先祖の魂とも会えると信じているのだ。そのため、彼らは比較的死を恐れないほうで、死別の悲しみも大きく軽減されている。ティフォンもまさにそうした心構えでサーミの荒野を駆けまわっているのである。ゆえに、両親は今もどこかで自分を守ってくれていると、彼女は信じているのだ。
ティフォンは今でも、時折同じ内容の悪夢を見ることがある。その夢の中で、彼女は様々な種類のか弱く小さい獣となり、視界に収まり切れないほど大きな影に狩られてしまうのだ。自身の巣が壊され、親族が骨だけにされる光景は何度も何度も見てきたという。我々は始め、現代医学の視点から分析を行い、ティフォンの記憶喪失はトラウマによって自身の記憶を一部封じてしまったことが原因であると考えて、彼女と話し合ってみた。すると、両親に対しおぼろげながらも恋しさを抱いていたティフォンは、記憶を取り戻すことに前向きな反応を示し、トラウマを掘り起こすことによる苦痛も恐れていないと述べた。そこで、彼女の同意を得て、我々はティフォンに初歩的な検査を行った。しかし残念なことに、結果として、ティフォンは解離性健忘症でもなければ、脳へのダメージによって記憶機能が損なわれたというよく見られるパターンでもなかった。「厄災」がもたらす何らかのダメージは、現存の医学機材で捉えられるものではないと、そう結論付けてほぼ間違いないだろう。その後、ケルシー医師の要請があり、我々はティフォンに対するさらなる調査を中止した。
いずれにせよ、ティフォンは今のところ元気に暮らしており、自分の記憶喪失を異常だと思ったこともない。彼女はただ、忘れてしまった両親の温もりを恋しく感じているだけだ。テラ大陸における大多数の地域での死生観とは異なり、サーミ人は死者となることを、ただ身体という器が動かなくなっただけと捉えている。そして、儀式を一通り行えば、魂は自由にこの世を漂うことができ、先祖の魂とも会えると信じているのだ。そのため、彼らは比較的死を恐れないほうで、死別の悲しみも大きく軽減されている。ティフォンもまさにそうした心構えでサーミの荒野を駆けまわっているのである。ゆえに、両親は今もどこかで自分を守ってくれていると、彼女は信じているのだ。
幼獣は父母の死を目にしてしまえば、成獣になったあと敵討ちをしに行く。たとえ草食獣でも、捕食者の腹を無理やり突き破ってでもそれをかなえるのだ。
ティフォンは長年、その日のために黙々と準備をしてきた。誰より経験豊富な狩人の後ろについては技をまね、山岩の隙間に隠れては北地の戦士たちの訓練を見つめ、またアルゲスにも知識を求めて――幼い子供が心に潜めた大きな決意を見抜いたのは、恐らくアルゲスだけだろう。しかし、サイクロプスはいつも通り、彼女の行動を咎めはしなかった。
最終的に、ティフォンの前に残された問題は一つだけになった――いかにして仇を見つけ出すか、ということだ。
彼女はそれが果てしなく長い旅になるだろうと思っていた。だが実際には、その考えが芽生えた瞬間に、その時は訪れた。
正確に言えば、敵のほうが彼女を見つけたのだ。ティフォンはただ、背負った黒い弓に異常な重みを感じ取っただけだった。
己の「感覚」に従い、ティフォンは初めて、悪魔の穢れを受けた獣を見つけた。以来、彼女はそうした獲物を狩ることを自身の責務とみなすようになったのだ。
そして、この戦いは今も続いている。
ティフォンは長年、その日のために黙々と準備をしてきた。誰より経験豊富な狩人の後ろについては技をまね、山岩の隙間に隠れては北地の戦士たちの訓練を見つめ、またアルゲスにも知識を求めて――幼い子供が心に潜めた大きな決意を見抜いたのは、恐らくアルゲスだけだろう。しかし、サイクロプスはいつも通り、彼女の行動を咎めはしなかった。
最終的に、ティフォンの前に残された問題は一つだけになった――いかにして仇を見つけ出すか、ということだ。
彼女はそれが果てしなく長い旅になるだろうと思っていた。だが実際には、その考えが芽生えた瞬間に、その時は訪れた。
正確に言えば、敵のほうが彼女を見つけたのだ。ティフォンはただ、背負った黒い弓に異常な重みを感じ取っただけだった。
己の「感覚」に従い、ティフォンは初めて、悪魔の穢れを受けた獣を見つけた。以来、彼女はそうした獲物を狩ることを自身の責務とみなすようになったのだ。
そして、この戦いは今も続いている。
HP
1702
攻撃力
1155
防御力
113
術耐性
0
配置コスト
24
攻撃間隔
2.4 秒
ブロック数
1
再配置時間
70 秒
素質
- 鋭牙の如く連続攻撃時、敵の防御力を最大50%まで無視できる(攻撃するたびに防御力無視の割合+10%)。8秒間攻撃せずにいると効果がリセットされる
- 泥沼の如くスキル発動中、同じ敵に初めてダメージを与える際、攻撃力が160%まで上昇し、3秒間足止め状態にする
スキル
設定で詳細一覧を有効にして、詳細データが表示されます。
 迅速攻撃γ自動回復手動発動初期SP15必要SP35継続時間35 秒攻撃力+45%、攻撃速度+45atk0.45attack_speed45
迅速攻撃γ自動回復手動発動初期SP15必要SP35継続時間35 秒攻撃力+45%、攻撃速度+45atk0.45attack_speed45 氷原の掟自動回復手動発動初期SP42必要SP50継続時間20 秒攻撃力+50%、攻撃するたびに矢を2本放ち(違う対象を優先して攻撃)、さらに40%の確率で対象を1秒間スタンさせる
氷原の掟自動回復手動発動初期SP42必要SP50継続時間20 秒攻撃力+50%、攻撃するたびに矢を2本放ち(違う対象を優先して攻撃)、さらに40%の確率で対象を1秒間スタンさせる
2回目以降スキル使用時は退場まで効果継続atk0.5attack@prob0.4attack@stun1first_duration20 「永久なる狩猟」自動回復手動発動初期SP25必要SP40攻撃範囲内の敵を1体マークする。攻撃間隔が大幅に延長し、通常攻撃が対象へ矢の雨を降らせる攻撃に変化する。矢の雨はマークした対象の周囲にいる敵をランダムで攻撃し、攻撃力の175%の物理ダメージを5回与え、さらに対象を0.4秒スタンさせる
「永久なる狩猟」自動回復手動発動初期SP25必要SP40攻撃範囲内の敵を1体マークする。攻撃間隔が大幅に延長し、通常攻撃が対象へ矢の雨を降らせる攻撃に変化する。矢の雨はマークした対象の周囲にいる敵をランダムで攻撃し、攻撃力の175%の物理ダメージを5回与え、さらに対象を0.4秒スタンさせる
合計10発の弾薬を撃ち切るとスキルが終了(手動でスキルを停止可能)base_attack_time3.1attack@s3_stun0.4attack@s3_atk_scale1.75attack@s3_trigger_time10attack@s3_max_hit_num5
モジュール
 ORIGINALティフォンの記章
ORIGINALティフォンの記章 ティフォンは距離を保って火力で大型の敵を制圧することに秀でている。
ティフォンは距離を保って火力で大型の敵を制圧することに秀でている。
外勤部門の決定に基づき
外勤任務においては狙撃オペレーターとして区分し、破城射手の責務を担う。
特別に本記章を授与し、
その証明とする。 SIE-X自然の容認
SIE-X自然の容認STAGE ステータス 強化説明 1 - HP +120
- 攻撃力 +60
破城射手の特性 重量が最も重い敵を優先して攻撃重量ランクが3以上の敵を攻撃時、攻撃力が115%まで上昇2 - HP +180
- 攻撃力 +78
鋭牙の如く 連続攻撃時、敵の防御力を最大55%まで無視できる(攻撃するたびに防御力無視の割合+11%)。8秒間攻撃せずにいると、効果がリセットされる3 - HP +210
- 攻撃力 +90
鋭牙の如く 連続攻撃時、敵の防御力を最大60%まで無視できる(攻撃するたびに防御力無視の割合+12%)。10秒間攻撃せずにいると効果がリセットされる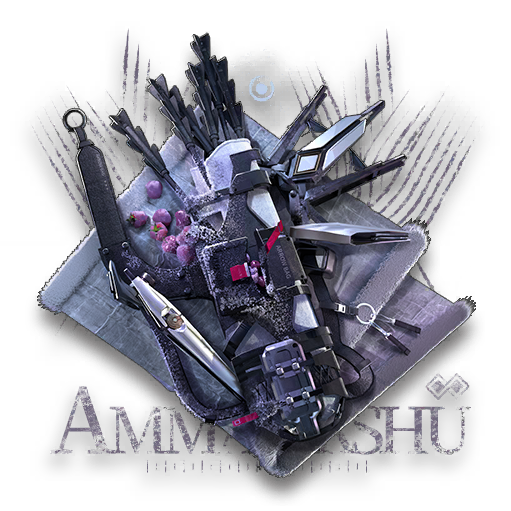 背の高いフェルトハットをかぶり、毛皮の襟巻で顔のほとんどを覆い隠したとある夫婦が足を止めた。
背の高いフェルトハットをかぶり、毛皮の襟巻で顔のほとんどを覆い隠したとある夫婦が足を止めた。
それから彼らは慎重に、恭しく荷物から血の滴る肉を取り出し、その血を木の根に垂らした後、肉を枝へと吊るす。
そうして彼らは、曖昧で、自分たち自身意味をよく理解していない音節の連なりを唱え始めた。
そんな中、彼らの娘はそう遠くない辺りにいて、のろのろと夫婦に付いてきていた。
彼女は両親と手を繋ぎたいと思ったが、あいにく両手は塞がっている。
今日は彼女にとって初めて、大人のように武器を携えて外へ出た日だったのだ。
武器を持つことは戦うことを意味しており、戦うのならば油断は許されない、という両親の教えに従い、彼女は矢をつがえたまま弓を持ち歩いていた。
「あの子にも、いずれはこういうことを教えてあげないと。」と、母の声が言った。「弓の引き方やナイフの研ぎ方、罠の仕掛け方、それから、恐れを抱かないこと、どんなものにも対抗できる力を身につけること……そうしなければ生きてはいけないということも。だって、私たちがサルカズであることはいずれ気付かれてしまうでしょう。そうなれば、サルカズを受け入れてくれる場所なんてどこにもないのだから。」
「だが、もう昔の生活には戻らないと約束したじゃないか。」今度は父の声が聞こえた。「それに……あの子とも約束していただろう?確かあの日は虹が出ていて、私は森に入って膝鎧でそれを受け止めていたな。覚えているか?」
「その時あの子はまだ生まれてもいなかったじゃない……はぁ、まあいいわ。」母の声がずいぶんと柔らかくなった。「さっき言ったようなことはもちろん教えるけれど、祈りも捧げるようにしましょう。たとえ、サーミの地にサルカズへの祝福を請うのが荒唐無稽なことだとしてもね。とにかく、私たち脱走兵は連中に見つかりさえしなければそれでいいのだし……」
娘はふと、道端に佇む粗末な木彫りに気を引かれて足を止めた。
聞こえていた両親の声は徐々に遠ざかっていく。
木彫りが指し示す方向には、必ず良いものがたんまり置かれた木のうろがあることを彼女は知っていた。
何か家に足りないものがあり、それを手に入れる術がない時、両親がよくそんな木のうろを探していたからだ。
彼女は色鮮やかな飾り結びが欲しくなり、木彫りが示す方向へと、狭い木々の隙間を縫って進んだ。
その道すがら、木のうろでの物々交換に使うため、果実やきれいな石など、ぴんと来たものを拾っては矢筒に入れながら。
けれどそうしているうちに、いつの間にか彼女は野獣が潜む森へと足を踏み入れていた。
……
時が経ち、サルカズの少女はそんな幼い頃の経験をすべて忘れてしまっていた。
両親が自分を探して呼んだ名前も、両親を驚かせようと手を見せた時、そこに結んでいた飾り結びの色も――
その時の両親の反応すらも。
「見てくれ、この子を生かしてくれたのは……」
男は娘の矢筒を指さして、信じられないという顔で愛する妻を呼び寄せた。
その中にサルカズの夫婦が見たものは、小さな矢筒の底に残った、雪の塊が融けたかのような湿った跡だった。
基地スキル
 氷原の足跡応接室配置時、手がかり捜索速度+10%。他のサーミオペレーターと同時に応接室に配置された場合、追加で手がかり捜索速度+5%、自身の1時間ごとの体力消費量+0.5
氷原の足跡応接室配置時、手がかり捜索速度+10%。他のサーミオペレーターと同時に応接室に配置された場合、追加で手がかり捜索速度+5%、自身の1時間ごとの体力消費量+0.5 実戦技術:破城射手
実戦技術:破城射手 訓練室に協力者として配置する時、狙撃の訓練速度+30%。訓練者の職分が破城射手である場合、訓練速度がさらに+45%
訓練室に協力者として配置する時、狙撃の訓練速度+30%。訓練者の職分が破城射手である場合、訓練速度がさらに+45%